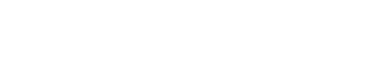ACTIVITY BLOG活動ブログ
2025.11.21 消費者問題に関する特別委員会での質疑 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)
○福島みずほ君
立憲民主・社民・無所属共同会派、社民党の福島みずほです。
まず、香害、香りの害について質問をいたします。
PIO―NETに来ている香害の相談件数は減少していません。たくさんの人が苦しんでいます。効果的なポスターに改善してほしい。お手元に配付資料配っておりますが、これは日本消費者連盟のものです。まさに、あなたのその香り香害かもというのなんですが、もっと分かりやすい効果的なポスターに改善してほしい。いかがでしょうか。
○国務大臣(黄川田仁志君)
いわゆる香害に関する消費生活相談が全国の消費生活センター等に一定数寄せられていることは承知をしております。
福島委員お尋ねの啓発ポスターについては、被害を訴えられておられる方々の声も踏まえまして、その香り困っている人がいるかもから、その香り困っている人もいますと表現を見直しを行ったところでございます。
周知啓発については、関係省庁と最新の科学的知見も含めながら情報共有を行ってまいりたいと思っております。
○福島みずほ君
人もいますと人がいますというのでも随分違うと思いますし、これくらいあると、あっ、こういういろんなものが香害の原因かもしれないし控えようかなと思いますので、是非、ポスター、効果的なポスターに改善してほしい。でないと、香害はなくならないと思います。
学術団体による子供の香害及び環境過敏症状に関する実態調査の中間発表によると、小中学校の約一〇%が香害被害を感じており、さらに不登校傾向にある子供が約二%いるとされています。
文科省は、そのような状況をどう捉え、香害にどう対策しているのでしょうか。
○政府参考人(神山弘君)
お答え申し上げます。
学校において香料等に起因して健康不良を訴える児童生徒がいることから、御指摘のようないわゆる香害に関する実態調査が行われていることは承知しております。一方で、厚生労働省において実施されている研究によりますと、その原因等についてはまだ十分に明らかになっておらず、疾病概念が確立していない状況と認識しております。
したがって、文部科学省といたしましては、現段階では、各学校において児童生徒等の訴えや症状に応じ個別の配慮を適切に行うことが重要であると考えております。そのため、その一助となるよう、関係省庁が協力して作成した先ほどの啓発ポスターですとか、いわゆる化学物質過敏症に関する教師用の資料といったものの活用を促しているという状況でございます。
○福島みずほ君
合理的配慮、個別的配慮と言いますが、教室の外で期末試験を受けている子供の事例があります。個別的にその子供を別のところでというのではなくて、そのような状況、どう捉えていらっしゃいますか。
○政府参考人(神山弘君)
文部科学省といたしましては、個別のケースごとの実態を承知しているものではございませんけれども、香料等に起因して健康不良を訴える児童生徒に対しては、個々の訴えや症状、また学校の施設や設備、体制等に応じて適切な環境を整えることが重要であると考えております。
文部科学省といたしましては、各学校において個別の配慮が適切に行われるよう、様々な機会を通じて周知に取り組んでまいりたいと考えております。
○福島みずほ君
個別配慮では教室の空気は汚染されたままになります。根本的な解決になりません。先ほどの学術調査では、学年が上がるごとに被害を訴える割合が増えているのが分かっており、根本的な解決をしなければ新たな香害被害を生む温床になるのではないですか。
○政府参考人(神山弘君)
お答え申し上げます。
学校におきまして香料等に起因して健康不良を訴える児童生徒がいることは承知しておるわけですけれども、その原因や病態、また発症機序等についてはまだ十分に明らかになっておりませんで、疾病概念が確立していない状況と認識しております。
現在、厚生労働省さんにおきまして研究が行われているものと承知しておりますので、引き続き、最新の知見の状況を注視するとともに、当該研究の進展等を踏まえて、学校における適切な配慮を促してまいりたいと考えております。
○福島みずほ君
子供たちには学ぶ権利もあり、健康に過ごす権利もあります。子供たちが香害被害に遭っている状況、やっぱりこれはゆゆしき事態だと思います。学校内での対策は子供の人権を尊重したものと考えますか。
○政府参考人(神山弘君)
文部科学省といたしましては、いわゆる香害の対応に限りませんけれども、児童生徒等が快適かつ健康に過ごすための環境を整えることが重要であると考えてございます。
そのため、個別のケースごとの様々な状況に応じてそうした環境を整えるために、各学校におきまして個々の児童生徒等の訴えや症状に応じた個別の配慮を行っていただいているところと考えてございます。
○福島みずほ君
これ、全然違うたばことも少し似ていると思うんですね。以前は予算委員会の傍聴席に灰皿がありました。議員会館内の会議室に灰皿の配置がありました。でも、そういうのはなくなりました。受動喫煙も問題で、空気を汚す、空気の中にたばこのその害があってはいけないということで大きく変わったわけです。そして、この香害の原因である化学物質を始め、いろんなものがやっぱり原因であり、そしてそのことが問題であるということはかなり広まってきた。
私は、やっぱり子供が学校で勉強できない、つらいって、大人になって、その間に症状を重くしていくというのは、本当に学ぶ権利を奪っていると思います。是非、例えば順繰りで給食のいろんなエプロンとか来るわけですが、そのときに柔軟剤やいろんなものを使わないでほしいというようなことをもっと徹底してほしいと思うんですね。
私は、母がちょっと香害に遭うような、ドラッグストアの洗剤の間を通ると涙がぽろぽろ出てくるような人だったので、ずっと石けん、合成洗剤は使わない、私は今も石けんと石けん液なんですね。だから、やっぱり隣の人でセーターから柔軟剤の匂いがばあっと出てくると、やっぱり、あっ、これ柔軟剤の匂い、ちょっとつらいなと私も思うんです。私は重い症状ではないけれど、全国いろんなところに行くと、この香害があって外に出られない、交通機関に乗れない、仕事に行くのもつらいという声を聞くんです。だったら、それをなくしていく。
で、今日の質問はとりわけ子供なんです。子供はこういうことにとても鋭敏ですし、子供の実際一〇%あるということを変えたいんですね。だから、広報してもらう、使うなというのは難しくても、こういうことを知ってほしいと言うだけでも学校の現場が変わると思うんですね。空気を、空気というか、部屋の中の空気を変えなくちゃいけないと思っているので、是非、文科省、もう一歩進んでやってくれませんか。
○政府参考人(神山弘君)
お答え申し上げます。
いわゆる香害につきましては、先ほど申し上げたように、その原因などが科学的に明らかになっていないという状況でございますので、全国一律に学校における遵守事項などを定めることは困難だというふうに考えてございます。
他方、香料等に起因して健康不良を訴える児童生徒がいることは事実でございますので、各学校におきまして、例えば、教室等に不快な刺激や臭気がない状態を保てるよう日常的に換気をしていただくことに加えて、当該児童生徒に対して、個々の訴えや症状に応じた個別の配慮を適切に行うことが重要だと思ってございます。
文部科学省といたしましても、こうした取組が適切に行われるように、教育委員会等を通じまして、いわゆる香害に対する理解促進をお願いしているところでございまして、引き続き周知に努めたいと考えてございます。
○福島みずほ君
かなりでもはっきりしているじゃないですか。私は花粉症ですが、ある日から花粉症になりました。今香害の被害に遭っていなくても、ある日症状が出るかもしれない。としたら、今個別的配慮をするんじゃなくて、みんなが将来もかからないような環境を学校現場でつくるべきだというふうに思います。
保育園や学校など、子供が利用する施設や介護現場などでは無香料が基本であるべきではないでしょうか。
○政府参考人(水田功君)
お答えいたします。
保育所等において子供の心身の健康と情緒の安定を図るために、子供が心地よく過ごすことができるような環境をつくることは大変重要でございます。こども家庭庁では、保育所保育指針において、施設の温度、湿度、換気、採光、音などの環境を常に適切な状態に保持するとともに、施設内外の設備及び用具等の衛生管理に努めることが大切であることを示しております。
香りの強さの感じ方には個人差があり、不快に感じる人もいることから、香りのマナー啓発を推進するため保育所等へ啓発ポスターを周知しているところでございまして、今後とも保育所の適切な環境づくりに努めてまいりたいと考えております。
○政府参考人(林俊宏君)
介護現場における取組についてお答え申し上げます。
介護現場において香りで困っておられる利用者さんがいることは事実でございまして、香り付き製品の使用に当たって、周囲の配慮を求める観点から、啓発ポスターについては都道府県を通じて介護、高齢者施設等に対して周知を行っております。
また、訪問系サービスについては個別の配慮というのも必要でございますので、利用者から聞き取って個別に配慮したサービス提供を行うように、これも事業者に周知をさせていただいております。
こうした取組を通じまして、介護現場に対して香り付き製品の使用に関する理解が深まるように引き続き取り組んでまいります。
○福島みずほ君
マイクロカプセルの規制をすべきではないかという、このポスターにもありますが、マイクロカプセルはずっと付いていて、いつまでもいつまでもその匂いを出すというふうになります。
マイクロカプセルの規制がEUであるかどうかというのはずっと議論になっておりますが、前回の質問において、経産省は、引き続き、関係省庁や業界と連携しながら、香りによる健康への影響などを注視して対応してまいりたいと答弁をしました。厚生労働省は、今後とも周知啓発を進めるとともに、関係省庁と連携し、関連する研究などの科学的知見あるいは海外の状況を注視し、情報収集に努めてまいりたいと答弁しています。
それぞれ、経産省、厚労省、その後に何をしてきたのか教えてください。
○政府参考人(畑田浩之君)
お答え申し上げます。
EUにつきまして、今御指摘のありました規制は、マイクロプラスチック利用に伴うこれは環境への影響等を考慮して導入される措置でありまして、香りによる健康への影響に対するものではないというふうに理解をしております。
事業者に対してマイクロカプセルの使用を規制すべきという御指摘がございましたけれども、マイクロカプセルを使用した柔軟仕上げ剤等の香料の成分が健康に与える影響、これが科学的に明らかにされていないという状況に変化はないというふうに理解をしておりまして、そのため規制には慎重な検討が必要との考えに変わりはございません。
こうした間、経済産業省としては、香りに関する消費者の声、これを踏まえまして、関係省庁と連携して、先ほどの啓発のためのポスターですね、などを通じた情報提供に努めてきておりまして、具体的には、前回の答弁以降、我々としては、洗剤業界、それから香料の業界、小売業界、家電業界、こうした業界団体十五団体を通じて消費者に向けて周知を図っておりますし、またさらに関係業界に対しては製品パッケージへの表示、それからホームページでの香料成分、これを表示することにつきまして引き続き指導をしてきたところでございます。また、関係省庁、業界を通じて最新の科学的知見の情報収集にも努めてきたところでございます。
引き続き、最新の科学的知見を踏まえまして、関係省庁、業界と連携して対応してまいりたいと考えております。
○政府参考人(佐藤大作君)
マイクロカプセルの規制に関するお尋ねということでございます。
家庭用品に使用されるマイクロカプセルやそれに含まれる香料が健康に与える影響は、科学的には明らかにされていないものと承知しております。このため、現時点でその使用を規制することは難しいと考えております。
その上で、柔軟剤等に含まれる香料によって頭痛、吐き気などの諸々の症状が生じるという声があることは承知してございます。
まずは、化学物質過敏症について、症状出現に関する契機や症状出現時の脳活動の状況、併存疾患の治療による化学物質過敏症の症状改善の程度など、病態の解明に向けた調査研究を行っております。
そのような研究の結果が得られた際には、その結果も踏まえて、関連する研究等の科学的知見や海外の状況を注視することとしておりまして、引き続き、医療関係者等との情報共有も行い、適切な情報収集に努めてまいりたいと考えております。
○福島みずほ君
原因はかなりもうはっきりしていますし、厚生労働省の研究結果もあります。被害に遭う人をなくすこと、将来の被害者もなくすことはとても重要ですし、今日特に申し上げたのは、子供たちの健康と学ぶ権利を守ってほしい、文科省ももう一歩踏み込んでやっていただきたいと思います。是非、それぞれの省庁が香害をなくすためにもう一歩踏み込んで、消費者庁も表示も含めて検討してくださるように心からお願いをいたします。
ですから、香害の担当の答弁者の方は退席されて結構です。ありがとうございます。
次に、ごめんなさい、ちょっと早いですかね。(発言する者あり)ありがとうございます。
○委員長(松沢成文君)
ちょっとお待ちください。
佐藤審議官と林審議官は退室して結構です。畑田審議官も、あと水田審議官もそうですね、は退席して結構ですので。
○福島みずほ君
済みません。
公益通報についてお聞きをいたします。
公益通報者が不利益な配置転換をされた場合の罰則の規定がありません。懲戒解雇した場合のみならず、不利益な配置転換がなされた場合にも罰則を設けるべきではないですか。
○政府参考人(飯田健太君)
お答え申し上げます。
令和七年の公益通報者保護法の改正におきまして、公益通報を理由とする解雇又は懲戒に対する罰則の導入、それから立証責任の転換など、大幅な見直しを行ったところではございます。
御指摘のような公益通報を理由とする配置転換への罰則などについての検討に当たりましては、これの国会審議の、改正法の審議に当たりましても御議論になったと承知しておりますけれども、その際にも裁判例等の立法事実の蓄積、それから我が国の雇用慣行、労働法制上の取扱い、労働訴訟実務の変化などを踏まえる必要があるというふうに考えてございます。
まずは、改正法の施行に向けた取組を適切に進めるとともに、その効果や影響、さきに申し上げました検討事項に関する実態を十分に把握、注視してまいりたいと考えております。
○福島みずほ君
是非、懲戒解雇をした場合のみならず、不利益な配置転換がなされないよう罰則を設けてほしいということを強く要望します。
二〇二五年の改正の際には、公益通報により不利益取扱いを受けた当事者が検討会の委員に入っていませんでした。次回の改正に際しては検討会に入れるよう求めますが、いかがですか。
○政府参考人(飯田健太君)
お答え申し上げます。
御指摘の公益通報者保護制度検討会でございますけれども、制度をめぐる近年の国内外の動向を踏まえまして、法学的見地あるいは実務の観点から制度の実効性向上に向けた課題と対応を検討するために、学界、労働団体、消費者団体、経済界といった各界の代表者や通報者を支援している弁護士の方々を委員といたしました。
検討に当たりましては、通報を理由とする不利益な取扱いが争点となった近年の裁判例を参照したほか、日本弁護士連合会で公益通報について広く扱っている消費者問題対策委員会の委員の方からの御意見もいただいておりまして、通報者の状況もしっかり踏まえた議論が行われたと考えております。
今後の法制度の検討におきましても、特定の事案だけでなく、関係する様々な事案を比較検討することが重要であると考えておりまして、通報を経験した方々の状況も十分に踏まえてまいりたいと考えております。
○福島みずほ君
通報対象事実の存在を証明するために資料を収集、持ち出しする行為には、免責、通報のために必要で社会的相当性を逸脱せず、通報以外の目的には使用しない資料の収集、持ち出しを免責する規定の導入が必要ではないでしょうか。
○政府参考人(飯田健太君)
お答え申し上げます。
公益通報の証拠となる資料でございますけれども、これ事実関係を調査するために重要な位置付けを占める一方で、通報者による内部資料の収集や持ち出しは事業者の情報管理ですとか組織の秩序に悪影響を及ぼすと、こういう場合もあるかと考えております。
裁判所におきましては、通報との関連性や通報者の動機、行為の態様、影響、こういったことを総合的に勘案いたしまして判断されていると承知しております。
このため、公益通報のための資料収集、持ち出し行為につきまして、一定の要件の下に免責する規定を設けるということは現状困難であると考えておりまして、事案ごとに事情を総合勘案の上判断することが適当と考えております。
○福島みずほ君
公務員の公益通報が守秘義務違反と言われる可能性があると、公務員は刑訴法二百三十九条二項で告発義務を課されているにもかかわらず、違法行為の通報をはばかってしまうということがあります。刑事免責規定が必要ではないですか。
○政府参考人(飯田健太君)
お答え申し上げます。
国家公務員法あるいは地方公務員法などに規定する秘密でございますけれども、これは非公知の事実であって、実質的にもそれを秘密として保護するに値すると認められるものというふうに解されております。
公益通報の対象となる法令違反行為は、犯罪行為などの反社会性が明白な行為でございまして、秘密として保護するに値しないほか、公務員には刑事訴訟法の規定により犯罪の告発義務が課されていると、こういった趣旨にも鑑みますと、公益通報をしても守秘義務に反しないと考えられるところでございます。
こうした点につきましては消費者庁のウェブサイトにも掲載しているところでございますけれども、引き続き適切な周知に努めてまいりたいと考えております。
○福島みずほ君
パワハラ、セクハラは、犯罪行為若しくは過料対象行為、又は最終的に刑罰若しくは過料につながる法令違反行為でないため、通報対象事実とはなりません。しかし、パワハラ、セクハラで苦しんでいる人もたくさんおり、公益通報者保護法の保護対象になるよう通報対象事実に係る規定を変えるべきではないですか。
○政府参考人(飯田健太君)
お答え申し上げます。
いわゆるパワハラ、セクハラでございますけれども、これどのような措置をとるべきかというのはそれぞれの法令において判断されているというものと承知しておりますけれども、ハラスメント行為の相談を理由とする不利益取扱いにつきましては、労働施策総合推進法などのほかの法律で禁止されておりまして、全体として相応に保護する制度が存在しておりまして、別の枠組みで保護されるものと承知しております。
なお、ハラスメント行為が不同意わいせつ罪や暴行罪などの刑法犯に該当する場合には、その事実は通報対象事実に該当いたしまして、公益通報者保護法により通報者は保護されるという可能性もございます。
○福島みずほ君
時間ですので終わります。ありがとうございました。
※本議事録は未定稿です。