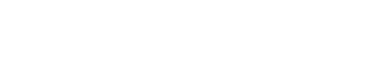ACTIVITY BLOG活動ブログ
2025.3.24 法務委員会での質疑 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)
○福島みずほ君
立憲・社民・無所属会派、社民党の福島みずほです。
まず、女性差別撤廃委員会への任意拠出停止についてお聞きをいたします。
外務副大臣は、記者会見より以前に任意拠出の停止などを知っていましたか。
○副大臣(藤井比早之君)
御質問の対応につきましては、政府として検討し、このような判断となったところでございまして、政府内の検討の詳細についてはお答えを差し控えたいと思います。
○福島みずほ君
違いますよ。政務官は事前に知らなかったと言いました。政府内部の議論を聞いておりません。副大臣は、記者会見より前に知っていましたか。
○副大臣(藤井比早之君)
繰り返しとなりますが、政府内の検討の詳細についてはお答えを差し控えたいと思います。
○福島みずほ君
知っていたということですか。
○副大臣(藤井比早之君)
繰り返しで恐縮でございますけれども、政府内の検討の詳細につきましてはお答えを差し控えたいと存じます。
○福島みずほ君
政府内のことなど聞いていません。副大臣が知っていたかどうかを聞いているんです。答えてください。
○副大臣(藤井比早之君)
これらの対応は、そもそも政府として対応を決めるものでございます。政府としての、政府内の検討の詳細についてはお答えを差し控えたいと存じます。
○福島みずほ君
おかしいですよ。詳細など聞いてないですよ。あなたが知っていたかどうかを聞いているんです。それは政務三役として言うべきですよ。どこまで関与したか言うべきじゃないですか。

○副大臣(藤井比早之君)
政府として検討すべきものでございます。その政府の検討の中身につきましては、詳細につきましてはお答えを差し控えたいと存じます。
○福島みずほ君
イエスかノーかだけです。そして国会ですよ。なぜこんな簡単なことも答えないんですか。何にも明らかにしないというのはおかしいですよ。民主主義を理解していないと思います。
次に、二〇〇五年前、二〇〇五年以降、任意拠出していないというのは分かっています。二〇〇四年、五年前も任意拠出していないんじゃないですか。
○副大臣(藤井比早之君)
過去の事例を網羅的に調査しているわけではございませんので、これまでの任意拠出金について全てお答えすることは困難でございますけれども、少なくとも平成十七年以降は、日本から国連人権高等弁務官事務所、OHCHRへの任意拠出金は女子差別撤廃委員会の活動に使用されてはおりません。また、確認できた範囲では、平成十七年以前につきましても、OHCHRへの任意拠出金が女子差別撤廃委員会の活動に使用された事例は確認されておりません。
○福島みずほ君
つまり、外務省は、一月末に、任意拠出をしません、来日プログラムについても二〇二四年度は中止しますと言ったんです。今の答弁で、拠出してないじゃないですか。二〇〇五年以降じゃなくて、その前も確認できてないから拠出してないんですよ。そして、訪日プログラムについても、その時点ではまだ何も決まっていなかったというのを、外務委員会、衆議院で答えています。つまり、珍妙な話なんですよ。任意拠出していません、ずうっとしていません、そして来日プログラムも決まっておりません。その中止ってどういう意味ですか。
この間も言いました、DV夫みたいじゃないですか。おまえは俺の気に障るようなことを言ったなと、許さない、だから金も出さない、生活費も出さない、養育費も出さない、遠足も中止だ、だって金払ってないし遠足の計画もないじゃないという話ですよ。
外務省、これ珍妙ですよ。決まってない、払ってないことの中止って何ですか。
○副大臣(藤井比早之君)
今般の判断により、今後、CEDAWの活動に使用されないことが確保され、我が国の本件に対する立場をより明確に示すこととなると理解しております。
○福島みずほ君
記者会見見てくださいよ。中止する、停止するって言ったんですよ。払いもしていなければ来日プログラムもないのに、その停止って何ですか。しかも、CEDAWに対してこういう態度を取ることは良くないですよ。
産経新聞の十一月一日の社説があります。「抗議と削除要請は当然だが、それだけでは不十分だ。削除に至らなければ、国連への資金拠出の停止・凍結に踏み切ってもらいたい。条約脱退も検討すべきである。」。これに引きずられたんじゃないですか。
○副大臣(藤井比早之君)
これらの対応につきましては、政府として検討し、このような判断となりました。政府内の検討の詳細についてはお答えを差し控えたいと存じます。
いずれにいたしましても、政府としては、皇位に就く資格は基本的人権に含まれていないことから、皇室典範において皇位継承資格が男系男子に限定されていることは女子の基本的人権が侵害されていることにはならず、女子差別撤廃条約第一条の女子に対する差別には該当しないと考えております。
さらに、我が国の皇室制度も諸外国の王室制度も、それぞれの国の歴史や伝統を背景に国民の支持を得て今日に至っているものでございまして、皇室典範に定める我が国の皇位継承の在り方は国家の基本に関わる事項であると考えておりまして、女子差別撤廃委員会が我が国の皇室典範について取り上げることは適当ではないと考えております。
○福島みずほ君
だから、何で拠出しないんですか。リヒテンシュタインもスペインも留保をして、王位継承については留保をして条約を批准しています。リヒテンシュタインに対しても、これは男女平等にすべきだと女性差別撤廃委員会は勧告をしています。でも、それを受け入れているじゃないですか。今のような議論をすればいいじゃないですか。
それから、まさに世論調査では、女性天皇を認めるべきが八割占めているんですよ。今日の答弁は、民主主義理解していないですよ。この産経新聞の社説に引きずられて、払ってもいない、決めてもいないものを提出するといって世界に恥さらして、ジェンダー平等について日本が後ろ向きだということをアピールした。で、国内に対して、まさにこういう人たちに対して、まあこういうってどういう人か分かりませんが、まさにアピールをしただけじゃないですか。間違っていますよ。
この間、政務官に来ていただきました。政務官は事前に知らなかったと言ったんですよ。副大臣は何で答えないんですか。そして、この間、政務官は、今後、個別具体的な状況に応じまして、様々な御意見をこれからもしっかりと踏まえつつ、総合的に判断をしてまいりますと答弁しました。
その後、総合的に判断ってあったんでしょうか。
○副大臣(藤井比早之君)
CEDAWとのやり取りにつきましてお答え申し上げますと、女子差別撤廃委員会、CEDAWによる審査におきましては、我が国の皇位継承の在り方は国家の基本に関わる事項であり、女性に対する差別の撤廃を目的とする女子差別撤廃条約の趣旨に照らし……(発言する者あり)
○委員長(若松謙維君)
答弁中です。
○副大臣(藤井比早之君)
CEDAWが我が国の皇室典範について取り上げることは適当ではない旨を説明してまいりました。審査終了後にはCEDAWに対して、皇室典範において皇位継承資格が男系男子に限定されていることは女子差別撤廃条約第一条の女子に対する差別には該当しない旨、我が国の立場を表明するとともに、強い遺憾の意を伝達してまいったところです。CEDAWに対しては、審査プロセス及び審査後にも我が国の考えを繰り返し丁寧かつ真摯に説明してまいりました。にもかかわらず、確定版として公表された最終見解においても、皇室典範に関する記述が維持され、削除要請が受け入れられなかったことは大変遺憾であり、そのことを重く受け止め、政府として検討し、このような判断となったところでございます。
政府といたしましては、個別具体的な状況に応じて様々な御意見をしっかり踏まえつつ、総合的に判断してまいりたいと思っております。その上で申し上げますと、現在、政府といたしましては、今般の対応について撤回する考えはございません。
○福島みずほ君
総合的に判断をするというのが何かと聞いたのに経過を御説明になって、ちょっと質問に応じた答弁になっていないというふうに思います。
総合的に判断をしてくださいよ。この間、国連で女性の地位委員会やいろいろあって、日本の政務三役のお一人は行って、日本はジェンダー平等を実現すると力強くおっしゃっています。それと全く矛盾をしているというふうに思います。
選択議定書の批准など、汚名挽回のためにもしっかり批准すべきだということを申し上げます。これはあくまでも撤回を求めていきますし、やってもいない任意拠出と決めてもいない訪日プログラムを停止するということの外務省の珍妙さは本当に異常だと思います。
副大臣、御退席してくださって結構です。ありがとうございます。
○委員長(若松謙維君)
退室して結構です。
○福島みずほ君
次に、独立行政法人男女共同参画機構法案についてお聞きをします。
施設設置型法人とせずというのはどういう意味ですか。
○副大臣(辻清人君)
福島委員の御質問にお答えします。
従来の国立女性教育会館は、法律上、女性教育指導者等に対する研修のための施設を設置すること及び当該施設を研修等の利用に供することなどを業務の範囲として定めています。一方で、今般の法案で設立を予定している男女共同参画機構は、このような研修施設を設置することなく、特定の場所や方法にとらわれず多様な研修そのほかの事業を展開していくことを業務としているため、法案の御説明等を行う際には、施設設置型法人とせずとしています。
○福島みずほ君
なぜ宿泊棟や研修棟を撤去するんですか。
○副大臣(辻清人君)
男女共同参画機構は、従来、国立女性教育会館が行ってきた事業から事業内容の高度化を図ることとしています。具体的には、オンラインの利点を生かした多様なスタイルの研修や民間施設等を活用した全国各地での宿泊研修、テレワークにより幅広い分野の専門家等の協力を得て調査研究を実施することなどを想定しています。
このように、特定の場所や方法にとらわれない多様な事業を展開するため、新法人に必要な機能を本館に集約することとし、老朽化し、また施設の利用が低迷している宿泊棟、研修棟、体育施設等の施設については、新法人としては保有せず、令和十二年度までをめどに撤去を目指すこととしております。
○福島みずほ君
それ、撤回してくれませんか。
これ、国立女性教育会館、嵐山にあり、もう私も何度も、多くの女性たちがここで集まり、外国からも人を呼び、研修やったり集会をやったり、それで、バリアフリーなんですよね。障害のある人たちも使える施設で、日本で唯一のナショナルセンターなんです。何でそれを宿泊棟、研修棟撤去なんですか。金額は微々たるものですよ、軍備費などに比べたら。
オンラインも重要です。全国に行くのも重要です。しかし、何でこれを切り捨ててオンラインだけでやるのか。やっぱりみんなが一堂に会して議論をすることの良さってあるんですよ。どうしてこういうところをけちるのかというのが分からないんです。
○副大臣(辻清人君)
今、男女共同参画に関する国の実施体制を強化する中で、各地の男女共同参画センターを強力に支援していくためには、ハード中心からソフト中心の機関への転換を進める必要があると考えていまして、現在の施設の利用が低迷する中、その維持管理には年間修繕費等に平均して大体二、三億円を要しており、清掃や警備のために年間一億円弱の委託費も必要です。政府としては、時代の変化に対応し、法人の機能をより有効に発揮しやすい組織、業務に応じた施設の在り方として、新法人では施設を保有しないこととしたものです。
○福島みずほ君
撤回してください。
神奈川の女性センターも江の島から藤沢に移りとか、どんどん機能が縮小していったんですよね。やっぱり宿泊があり、研修棟があり、みんながそこで集まれる、世界中から集まれるんですよ。これ極めて重要で、今おっしゃったように、二、三億じゃないですか。コロナのときには確かにオンライン、オンラインも大事です。やったらいいですよ。でも、オンラインだけだったら集えないんですよ。草の根でみんなが集まるところがなくなる。
唯一のナショナルセンターで一億、二億が出せないって残念ですよ。防衛予算なんかに比べたら本当に微々たるものじゃないですか。唯一のナショナルセンターなんですよ。この撤回求めます。宿泊棟、研修棟を残してください。これ本当に残してください。そのことを強く申し上げます。
副大臣、退席していただいて結構です。
○委員長(若松謙維君)
辻内閣府副大臣は退席して結構です。
○福島みずほ君
次に、杉田水脈さんの人権侵犯の問題についてお聞きをいたします。
これについて、法務省の人権擁護局が人権侵犯について結果を出しました。法務局から申立人側に届いた通知書には、いずれも、調査の結果、人権侵犯の事実があったと認められましたとはっきり明記されています。ところが、杉田水脈さんは、自民党の三月九日の大会後、記者団に対して、法務局から人権侵犯の認定は受けておりませんと言ったという報道があります。
一般論として結構です。申立人に人権侵犯の事実があったと言ったんだったら、申し立てられた相手方にも人権侵犯の事実はあったというのは、これは届いているということでよろしいですね。
○政府参考人(杉浦直紀君)
お答えいたします。
一般論として申し上げますと、人権侵犯事件の手続において、申告者及び人権侵犯をしたとされる相手方に対して処理結果を通知する場合には、例えば人権侵犯の事実があったと認められるか否かについては、同一の内容を通知することとしております。
○福島みずほ君
同一の内容が行っているんだったら、申立人に人権侵犯の事実があったというのが来ているんだったら、相手方、杉田水脈さんにも人権侵犯の事実があったというのが届いているわけですよね。
じゃ、何でそれが人権侵犯の、人権侵犯の認定は受けていないというふうに言うのか。これ、人権擁護局、人権侵犯の事実があったと法務局が認定していることが本人に伝わってないということでしょうか。 個別の人権侵犯事件につきましては、その存否も含めて、お答えすることは差し控えさせていただきます。
○福島みずほ君
ただ、今日、一般論として、人権侵犯の事実の認定が両方にちゃんと行くと。だとしたら、杉田水脈さんにも間違いなく人権侵犯の認定は行っているはずなんですよ。それを人権侵犯の認定は受けていないというのは間違っているし、理解していないし、それから反省もしていないということで、大問題だと思います。
過日、杉田水脈氏の差別的発言に強烈な違和感があると、石破首相が、参議院の候補者予定として責任ある言動を求めると、これは予算委員会で言いました。
大臣、人権擁護局を、担当を持つ法務大臣として、この杉田水脈さんの様々な発言、とりわけ人権侵犯として認定された事案について、大臣、どう思われますか。
○国務大臣(鈴木馨祐君)
石破総理の予算委員会での発言については承知をしております。
その上で、国会議員であった方の個別の言動についてということで、所管の大臣として、法務大臣としてこの場でコメントをすることについては、申し訳ございませんが、差し控えさせていただきたいと思います。
○福島みずほ君
所管の大臣だからこそコメントすべきじゃないですか。だって、人権侵犯って法務省認めているんですよ。
○国務大臣(鈴木馨祐君)
総理があの場で所感を述べられたということについては承知をしておりますが、法務大臣としてということで、その個別の国会議員、個人の発言についてということにもなりますので、この場でそういった評価については、大変申し訳ございませんが、差し控えさせていただきたいと思います。

○福島みずほ君
意味が分かりません。人権侵犯の事実と法務局が認定し、両方にそれが行っていて、なぜその人権侵犯の、重いじゃないですか、重いじゃないですか。それについて一切法務大臣がコメントできない。
石破首相と同じ考えですか。
○国務大臣(鈴木馨祐君)
一般論について、事実関係ということではなくて一般論についてということであれば、先ほど局長から答弁をさせていただいたとおりでございます。
石破総理、私も、これはどういうお立場からということは私は承知をしておりませんけれども、そうした御発言をされた、そういった所感を述べられたことは私は承知をしております。
ただ、その上で、この場は法務大臣として答弁ということでございますので、その個々の国会議員の発言についてということでのそういった所感であったりそういったことについては、大変申し訳ございませんが、差し控えをさせていただきたいと思います。
○福島みずほ君
大臣、せっかく人権擁護局が人権侵犯と認定し、こういう発言問題だってやっていて、法務大臣がコメントできないというのはおかしいですよ。人権をなくすのが法務省の仕事でしょう。
もう一つ聞きます。
石破大臣は、あらゆる差別をなくすことが、なくすのが自民党だと言いました。社民党と一緒です。あらゆる差別をなくす。あした、同性婚について大阪高裁で判決が出ます。あらゆる差別なくすんだったら、同性婚、選択的夫婦別姓、法務省として出すべきじゃないですか。
○国務大臣(鈴木馨祐君)
石破総理が申しましたように、あらゆる差別をなくす、これは当然のことであろうと思います。
その上で、現在の様々係属中のことでもございますので、個々のことについて私からこの場で発言をすることについては、申し訳ございませんが、差し控えさせていただきたいと思っております。
○福島みずほ君
個々のことじゃなくて、同性婚、それから選択的夫婦別姓は間違いなく人権の問題です。法の下の平等に反すると、同性婚、言われ続けているじゃないですか。法務省、人権擁護局を抱える法務省としては踏み込むべきですよ。そのことを強く、閣法で出すべきだということを強く申し上げます。
次に、政治と金の問題について一言大臣にお聞きをいたします。
今まさに企業・団体献金の禁止やるべきだと社民党は考えています。また、野党の多くはそう考えている。それから、政治資金パーティーもやめるべきだと考えています。大臣規範があって、私が大臣のときも全くそういうパーティーやりませんでした。
大臣、これから政治資金パーティーをおやりになると報道されていますが、問題じゃないですか。
○国務大臣(鈴木馨祐君)
御指摘の件につきましては、私として従前から開催をしているものでありまして、会費五千円ということで、ある意味、地域の皆様方と幅広く集まっていただいて意見交換をするということでこれまでも開催をしているものであります。
そういった意味で、そうしたことと同規模ということでございまして、これは別に大規模に集金をするとか政治資金を得るという目的ということではなく、これ当然、法律上、政治資金パーティーになりますけれども、そこは、そうした、そういった政治資金を集めるという趣旨ということよりも、むしろ地域の方々と様々な形で意見をいただくということが中心の会でございます。そういった趣旨の中で大臣規範等に、大臣等規範に抵触するものとは考えてはおりません。
○福島みずほ君
そういうお金を集めてやるパーティーも一切やりませんでしたよ、私は大臣だったときに。民主党政権のとき、民主、社民、国民新党のときは、やっぱり大臣規範に沿ってやれというのは批判もありましたし、ある程度みんな守った、批判もあったし、と思います。
でも、それ、もうどんどん自民党政権になって壊れていっている、その大臣規範なんかは全然守られてないというふうに思います。商品券の十万円もそうですが、全く政治と金の問題が起きているときにやはり問題であるということを強く申し上げます。
次に、女性差別撤廃委員会からの勧告についてお聞きをいたします。
たくさん勧告が、まあ六十項目出ているわけですが、国内人権救済機関についても出ています。大臣、これ実現すべきじゃないですか。
○国務大臣(鈴木馨祐君)
この国内人権救済機関、人権機構、こういったことの設立ということでありますけれども、以前、平成十四年あるいは平成二十四年にも新たな人権救済機関の設置等を内容とする法案、これを提出しておりましたが、その当時は衆議院の解散ということで廃案となっております。
ただ、そのとき様々議論がありました。これは賛否両方の議論が当時あったわけであります。そういった中で、こうした賛否それぞれの議論ある状況の中で、こうした議論の状況を踏まえながら、私どもとして検討を行っているところであります。
○福島みずほ君
婚外子差別撤廃について、出生届について、パラグラフ十一(b)、十二(b)など出ております。出生届はこれ変えるべき、摘出である子、摘出でない子という記載があります。
私は、夫婦別姓を選んだので事実婚で、子供は法律上は婚外子です。ですから、選択的夫婦別姓と婚外子差別撤廃をやらなければならないと思ってやってきました。住民票の続き柄差別裁判、戸籍の続き柄差別裁判、法定相続分の差別裁判の代理人の一人でした。住民票の続き柄欄は、三十年前、自治省が通達を変えてくれて、全て子に変わりました。しかし、戸籍の続き柄欄は残っていますし、出生届の記載欄もまだ差別が残っています。
大臣、これ、かつて法務省は法案作ったんですよ。で、議員立法として出して、僅差で成立しなかったという過去があります。子供のために初めて作る出生届、これ勧告も受けていますし、子どもの権利委員会からもよく言われています。どうか出生届、戸籍法の改正すべきじゃないですか。
○国務大臣(鈴木馨祐君)
今御指摘の法改正ということ、そのことで申し上げれば、現行でいうと、この法律婚主義を採用している制度の下で、嫡出である子と嫡出でない子との間には、民法上、嫡出である子は父母の氏を称して、そして嫡出でない子は母の氏を称するなど、子の氏等に関して異なる扱いがされているところであります。そこは御指摘のところでもあります。
そして、戸籍法上も、このような民法の規定を受けて、子が入籍すべき戸籍について、嫡出である子と嫡出でない子との間で異なる取扱いをしている、そういった状況であります。
この点について、最高裁の方で、平成二十五年の九月二十六日の判決、出生届出書に嫡出子と嫡出でない子の別を記載すべき旨を定める戸籍法の規定については合理的な差別的取扱いを定めたものではないと判断をしていると承知をしております。
こうした状況下で、現時点で出生届書のチェック欄を変更する予定は現在のところではございませんけれども、今委員の御質問にもございましたように、様々な御意見があるということについては承知をしております。どのような方策がこれから適切であるのか、その点についてはしっかりと考えてまいりたいと思っております。
○福島みずほ君
嫡出である子、嫡出でない子という言い方も差別的であると言われていますし、是非これを、出生届、まず戸籍法の改正を是非やっていただきたい。国会の中でも頑張ります。
次、パラグラフ四十七、四十八。複合差別、交差的差別についても何度もいろんなことを受けております。
法務省の受け止め、それから内閣府、第六次計画策定につなげてほしい。いかがですか。
○政府参考人(小八木大成君)
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、第三次男女共同参画基本計画におきまして初めて複合差別について規制されたと承知しております。我が国におきましては、日本国憲法におきまして基本的人権の尊重を規定し、人種や性別等による政治的、経済的、社会的関係における差別を禁止しております。
その上で、男女共同参画基本法第三条では、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されていることを旨として男女共同参画社会の形成は行われなくてはならないとして、同法に基づき閣議決定した男女共同参画基本計画に沿って、政府全体で総合的かつ計画的に取り組むよう努めておるところでございます。
現在、委員御指摘ございました次期基本計画でございます第六次の男女共同参画基本計画の策定に向けた検討を行っておるところでございまして、御指摘も踏まえまして所要の検討を進めてまいりたいと思っています。
○福島みずほ君
よろしくお願いします。
パラグラフ十七、十八。女性の司法アクセスについての勧告があります。
法務省、最高裁、いかがですか。
○政府参考人(堤良行君)
お答えいたします。
昨年十月に公表された国連女子差別撤廃委員会の最終見解に女性の司法アクセスという項目が含まれていることは承知しております。
法務省としましては、この最終見解の内容を十分に検討した上で、関係府省庁等とも連携して適切に対応してまいりたいと考えております。
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君)
お答えいたします。
裁判所といたしましては、これまでも、全国的な観点から各地に裁判所支部等を配置するとともに、ジェンダーをめぐる現状等について理解を深めるものを含む幅広い分野の研修を実施するなど、職員の能力向上支援も実施してきたところでございます。
今後とも、様々な要因を注視しつつ、司法サービスを充実させるべく検討してまいりたいと考えております。
○福島みずほ君
次に、難民についてお聞きをいたします。
難民なのですが、難民認定率、不認定率は、アフガニスタンを除くと九九%不認定、補完的保護はウクライナを除くと九七%と低いです。参与員制度も、三千百六十六件のうち十四人、〇・五%未満しか認定をされていません。
ところで、二〇二四年、難民不認定処分取消し訴訟で国側が敗訴した後に難民認定されたのは二件です。つまり、裁判で国側が敗訴、その後難民認定です。つまり、何回も難民申請して駄目で、裁判に訴えて、難民認定、国側が敗訴し、その後、難民認定されたケースが二件あるということです。送還停止効を外されて強制送還になった人は十九人います。つまり、もしこの二人も送還されていたら大変なことになったんじゃないか。いかがですか。

○国務大臣(鈴木馨祐君)
御指摘のように、二〇二四年に難民不認定処分取消し訴訟で国側が敗訴をした、そしてその後に難民として認定されたものが二件ある、そのとおりでございます。
一般論として、難民不認定とした処分後の事情を含め、様々な事情が考慮された結果としての判断でありますので、判決の前提となる処分の当否も含め、それぞれの判断についてコメントすることについては差し控えをさせていただきたいと思っております。
御指摘の送還停止効の例外については、既に二度の難民又は補完的保護対象者の不認定処分を受け、いずれの処分についても行政上確定した者は二度にわたり難民及び補完的保護対象者該当性の判断がされているということでありますので、そういった意味では、慎重な審査は十分に尽くされたと我々としては考えているところであります。
○福島みずほ君
しかし、裁判で国側が敗訴して、その後、難民認定されているんですよ。つまり、送還停止効をやって本国に帰して、本人たちがもし弁護人に、弁護士に会わない、あるいは裁判を起こさない、あるいは、もう我慢、もう仕方ない、つてがない、裁判を起こさなければ、この人たちは難民認定されていないんですよ。送還停止効は、やっぱり送還停止効を、停止していたのを外すということの問題点というのをやはりこれは明らかにしているんじゃないですか。
○国務大臣(鈴木馨祐君)
今御指摘の点について申し上げれば、例えばそれは三回目以降の申請であったとしても、難民等の認定を行うべき相当の理由がある資料を提出をいただければ、その送還についてはなお停止するということとしております。
そういったことでいえば、万が一にも保護すべき事情があるという者については送還をしないという仕組み、これは我々として担保していると考えております。
○福島みずほ君
この人たちは裁判を起こしたから難民認定されたんですよ、結果的に。裁判を起こさなければ帰されているわけで、送還停止効をやめるという、送還しないというのをもう送還しちゃうんだという、三回目まで、三回目の難民申請中でも帰すというのは、やはりこの例からも明らかに欠陥があるというふうに思います。
任意の取調べの可視化についてお聞きをいたします。
検察は、任意の取調べについて一部録画、録音すると発表しましたが、警察はどうされますか。
○政府参考人(松田哲也君)
お答えいたします。
警察におきましては、従前から通達において、任意事件の取調べを含め、取調べの録音・録画制度及び精神に障害を有する被疑者に係る取調べ等の録音、録画に該当しない場合についても必要に応じて録音、録画を実施する、することができるとしてきたところであります。
任意事件も含めた録音、録画の実施については、各都道府県警察において適切に対応されているものと承知しております。
○福島みずほ君
検察はこれから任意、いやいや、検察は、起訴相当になるのであれば任意捜査であっても録画、録音すると言っているわけです。で、現時点で警察で実施している任意の取調べの件数は数十件、五十程度だと聞いていますが、そうですか。
○政府参考人(松田哲也君)
お答えいたします。
令和五年度におきましては、任意の取調べの録音、録画については五十件実施しております。
○福島みずほ君
五十件、少ないですよね。
検察はこれから任意捜査について起訴相当のものであれば、見込まれるものであれば、録画、録音すると。警察が一番重要じゃないですか。まず警察で取調べを受けるわけで、ここ、こんなにたくさんあるのに、年間五十件しか任意捜査で録画、録音していないんですよ。これ、検察に合わせて、ちゃんと任意捜査においても録画、録音すべきじゃないですか。
○政府参考人(松田哲也君)
お答えいたします。
取調べの録音、録画につきましては、任意性の立証等に資する反面、被疑者の供述が得にくくなるといった弊害も認められることから、慎重に検討を行う必要があると考えております。
一方、さきにお答えしたとおり、警察においては従前から、通達において、任意事件の取調べについても必要に応じて録音、録画を実施することができるとしてきたところであります。各都道府県警察ではこの通達に基づいて対応してきたものと考えておりますが、警察における録音、録画の実施例も積み重ねられてきたところであり、こうした積み重ね等も踏まえまして、録音・録画制度を適切に運用するよう都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
○福島みずほ君
検察はやるのに警察はやらない、年間今五十件で、通知でやっているというのはやはり残念です。是非、警察において、任意捜査における録画、録音もしっかりやってください。お願いします。この委員会でも何度もまた質問します。人質司法を変えるために必要ですので、是非やってください。
次に、死刑制度についてお聞きをいたします。
全国、あっ、世界中で、二〇二三年、死刑を執行したのは十六か国、二〇二二年は二十か国、二〇二一年、二〇年は十八か国、二〇一九年は二十か国執行です。執行している国は本当に少なくなっています。
袴田事件は、まさに死刑か無罪かしかなかった。そして無罪になって、彼は無罪判決を獲得することができました。五人いるわけですね、死刑台から生還したと言われる人が、免田事件を含め、現在少なくとも五件あると。これね、袴田さん、弁護人がいなかったり本人が諦めたりお姉さんがいなかったり、いろんな事情からとっくの昔に処刑されていたかもしれないんですよ。これ死刑制度は、やっぱりいろんな理由から私は反対です。とりわけ、取り返しが付かないという問題がある。
イギリス、まさにイギリス大使から死刑制度を考える議員連盟で話を聞きましたけれども、一件やっぱり冤罪で処刑したケースがあって死刑を廃止します。大臣御存じ、ヨーロッパは死刑を廃止しています。オブザーバーステータスを持っているニュージーランド、バチカン、カナダもまさに死刑をやっていません。
日本、これやっぱり考え直すべきじゃないですか。
○国務大臣(鈴木馨祐君)
死刑制度については、今先生御指摘のことも含め、様々な意見があること、承知をしております。その一方で、まさにこの死刑制度の存廃、これは我が国の刑事司法制度の根幹に関わる重要な問題であります。そういった意味では、国民世論に十分に配慮をしながら、社会における正義の実現等々、種々の観点から慎重に検討すべきと考えております。
先般の、去年の十月に行いました世論調査におきましても、今、死刑もやむを得ないという回答をされた方が八三・一%おられました。そういった意味で、国民世論の多数は、極めて凶悪、悪質な犯罪については死刑もやむを得ないと考えている状況もあります。
同時に、多数の者に対する殺人であったりあるいは強盗殺人、こういった凶悪犯罪はいまだに後を絶たないということを考えれば、その罪責が著しく重大な凶悪犯罪については死刑を科すこともやむを得ないと私どもとしては考えておりまして、現在、こうした観点から、死刑を廃止することについては適当ではないと考えているところでございます。
○福島みずほ君
私の質問は、冤罪が起きたじゃないかということなんです。袴田さん、死刑か無罪かしかなかったんです。とっくの昔に死刑になっていたかもしれない。取り返しが付かないですよね。五人いらっしゃるんですよ、そういう人が。
だったら、根本的に考え直すべきではないか。どうですか。処刑したらもう戻らないんですよ。
○国務大臣(鈴木馨祐君)
まさにそうしたことでいうと、刑事裁判において死刑が言い渡される事件においては、必ず弁護人が付されて、厳格な証拠法則の下で慎重な手続によって事実認定、死刑選択の判断がなされておりますし、あるいは、三審制の下で上訴権が付与され、有罪の認定、刑の量定等について上級審による審判の機会が確保されているところであります。まさにそういった中で、死刑の執行については、再審開始事由、この有無等を慎重に審査した上で行われている状況もございます。
その一方で、先ほど申し上げましたように、やはり凶悪犯罪が後を絶たない状況もある中で、国民世論ということでいえば、やむを得ないとしている方が八〇%以上いらっしゃる状況でもあります。
そういった中で、私どもとしては、そうした死刑の廃止ということを現時点で考えるということではございません。
○福島みずほ君
フランスは、ミッテラン政権のときにバダンテールさんが死刑の廃止を決めました。どこも世論調査は結構死刑執行高いんですよ。しかし、政治的な決断として、問題がある、民主主義や人権の観点からどうかということで、御存じヨーロッパは死刑をやめています。韓国も死刑制度はありますが、死刑は停止していますよね。ですから、凶悪犯罪があるという問題と死刑の制度ということはやっぱり別の問題です。
それから、死刑の執行を当日朝に本人に告げる今の運用は、適切な手続によらなければ処罰されないと定めた憲法三十一条に反するとして、死刑囚二人が、当日告知の執行を受け入れる義務がないことの確認などを国に求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は十七日、訴えを不適法として却下した一審大阪地裁判決を取り消し、審理を差し戻しました。
当日、当日にしか死刑を、死刑を執行する朝に連れていく、それまで分からないんですよね。袴田さんは、隣にいた房の人が当日朝連れていかれるのが分かって、彼はもう一歩もだまされて出ないぞというので出なくなってしまった。あるいは、神経を本当に病んでしまった理由も、やっぱりいつ処刑されるか分からない、冤罪で苦しんでいるということがあると思います。狭山事件の石川一雄さんのお葬式に二十日に行きました。彼も一審死刑ですよ。諦めたら死刑執行されていたかもしれない。そんなものがたくさんある。
是非、法務省において、死刑について考えてもらいたい。日本はどんな国かと言われますよ。犯罪の引渡条約やいろんなときにも問題になるじゃないですか。是非十分議論していただきたい。国会でも議論します。国民の間でも議論します。法務省、この権力、権限持っているので、是非議論をしてください。検討してください。
それを強く申し上げ、質問を終わります。
※本議事録は未定稿です。
●質疑の動画(字幕付き)は下記からご覧になれます●