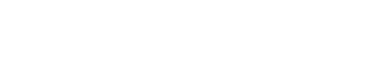ACTIVITY BLOG活動ブログ
2025.5.20 参議院 法務委員会での質疑 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)
○福島みずほ君
立憲民主・社民・無所属の福島みずほです。
受刑者に対して選挙権を認めるべきではないかということをまずお聞きをいたします。
これは、今までも様々裁判は提訴されて、違憲判決が大阪高裁では出ているわけですが、これは今最高裁に係属をしております。受刑者の選挙権で、これは長野刑務所で服役していた男性受刑者が、二〇二二年、公選法の規定は違憲だとして、損害賠償などを求めて国を提訴、今最高裁で上告中です。
諸外国ではもうかなりこの間変わってきて、受刑者に選挙権を認める国が増えています。ヨーロッパ人権裁判所の判決は御存じのとおりだと思います。カナダや南アフリカは違憲決定が出て変えました。そして、例えば二十二か国、ボスニア、カナダ、クロアチア、キプロス、チェコ、デンマーク、アイスランド、アイルランド、イスラエル、ラトビア、リトアニア、マケドニア、オランダ、ペルー、ポーランド、セルビア、スロバキア、北・南アフリカ、スペイン、スウェーデン、スイス、ウクライナなど、まさに受刑者に選挙権を認めています。
憲法改正のための国民投票法は、受刑者認めています。そして、まさに成年後見の被後見人に対して選挙権を与えないことに関して、まさに東京地裁で違憲判決が二〇一三年三月十四日に出て、七十四日後には法改正が成立し、七月の選挙で十三万人に選挙権が与えられました。
やっぱり選挙権、人間の根本的な権利です。これ、受刑者に選挙権与えるべきだ。大臣、いかがですか。
○国務大臣(鈴木馨祐君)
一般論として申し上げれば、受刑者の社会復帰、この観点というところから、社会のルールを決めるということに参画をする、あるいはルールを守ること、これを学ぶということ、これは極めて重要だと私ども考えております。その一方で、その受刑者に選挙権をということ、これは国民においても様々な御意見も当然あるんだろうと思っております。
そういった中で、この受刑者に選挙権認めるべきなのかどうかという点ということで申し上げますと、これは正直申し上げますと公選法という枠内での話になりますので、そういった意味で公選法、公職選挙法を所管をしていない私の立場からどうするべきだということ、これはお答えをすることなかなか困難だということは御理解をいただきたいと思います。
その上で、先ほど申し上げましたように、やはり国民の間にも様々なこれ当然御意見があろうと思います。そういった中で、この立法趣旨も含めて様々な観点から各党会派において御議論をいただくものかと私としては考えております。
○福島みずほ君
総務省の管轄でもありますが、刑務所内の処遇の問題でありますから、まさに法務省が解決すべきです。各政党が議論すべきことはもちろんですが、法務省で検討してくれませんか。
憲法改正の国民投票法では、投票権認められています。そして、六月一日から、あと十日後に、まさに懲役刑と禁錮刑が一本化されて拘禁刑になります。懲らしめのための刑罰から、今度、社会復帰、まさに再生のための、社会復帰のための制度に変わるわけです。社会の中の一員であるということをまさに理解する、社会に戻らないといけないわけですから、その意味で、まさに受刑者の選挙権、とっても重要だと思います。
法務省は、呼び捨て、それから番号で呼ぶんじゃなくて、君、さんで呼ぶようになりました、受刑者を。変わるわけですよね、人間関係も。尊厳というか、呼び捨てじゃなくて、それで変わる。選挙権を与えることで変わるんですよ。被後見人の人にも選挙権やっぱりあるべきだ、それで変わるんですよ。どうか法務省で検討してくれませんか。
○政府参考人(小山定明君)
お答えいたします。
法務省が所管でないということにつきましては、先ほど大臣から御答弁申し上げたとおりでございます。
拘禁刑との関係で申し上げましたら、受刑者につきましては、個々の特性に応じた矯正処遇や社会復帰支援を行うといったようなことによりその自覚に訴え、改善更生の意欲の喚起及び社会生活に適応する能力の育成を図るということが主眼となってまいりますので、その点も含めていろいろ検討がなされるものというふうに承知をしております。
繰り返しになりますけれども、最初に申し上げましたとおり、私どもの法務省の所管ではないということについては御理解をいただければと思っております。
○福島みずほ君
局長が今、検討されるべきとおっしゃったので、一歩前進だと思います。
拘禁刑ができて、懲らしめる場所から立ち直りを支援する場所に刑務所は変わるんですよ。だとしたら、やっぱり選挙権ちゃんと付与すべきだというふうに思っています。
今、世界も、それから日本の中でも、意識も物すごく今変わっています。やっぱりヨーロッパ人権裁判所や各国でどんどん認めていくということはとても大きい、勧告も含めてですね、というふうに思います。
そして、まさに、さっきも言いましたが、憲法改正のための国民投票も認めていますし、それから受刑者ですから、仮釈放中、例えば石川一雄さん、狭山事件の石川一雄さん、亡くなってしまわれました。しかし、彼、三十年間、一九九六年に仮出獄というか、仮釈放されましたから、三十年間社会にいたんです。でも、受刑者ですから、受刑者、仮釈放されていただけだから、選挙権なかったんですよ。社会に住んでいるのに選挙権がないんです。三十年間、彼は選挙権ありませんでした。そして、未決だったらあるのに、そしてそれで投票している人はいるんです、でも、受刑者になった途端にできない。これ、変えるべきじゃないですか。
局長、さっき少し前向き答弁してくださいました。刑務所の中における処遇の改善、本当に応援しています。いかがですか。

○政府参考人(小山定明君)
お答えいたします。
答弁自体は繰り返しになると思いますけれども、私どもといたしましては、先ほど申し上げていたとおり、六月一日から拘禁刑が導入されるということを踏まえて、いろいろな観点から検討する必要があるということを先ほど申し上げたところでございまして、先生におかれては、前向きとおっしゃいましたけれども、全ての観点を、いろいろな観点、例えば、私どもといたしましては、被害者の方のお話を承って、そのお話を受刑者に伝えて、その改善更生にというような観点もございます。
そういうようなところで、被害者の方の思いなどももしかすると観点には含めるべきというような御意見もあろうかと思います。いろいろな広い、幅広い観点からこれは検討されるべきだと思ってございます。
○福島みずほ君
局長、それ違うと思います。
権利は基本的人権じゃないですか。人間にとって最も重要な権利ですよ。普通選挙じゃないけれど、排除することは問題です。憲法改正のための国民投票法、認められているんですよ。これ、被害者の感情なんて言ったら、これ認めているのおかしくなるけれど、被害者の感情じゃないんですよ。
もちろん罪を犯すことは大問題です。しかし、懲らしめではなくて立ち直りのための場所に刑務所がなり、社会の一員だという認識、それをちゃんと持ってもらって、また社会に帰ってもらわないといけない。だからこそ、ちゃんとあなたは処遇する、ちゃんと有権者であるということは、本人のプライドもアイデンティティーも、人権の享有主体としてもとても大事だと思っています。
大臣は、様々な国民感情等々もありというふうに衆議院でおっしゃっているんですね。でも、それも越えて、是非法務省で議論してくださいよ。
是非、世界が今どんなふうに動いているのか、そして、拘禁刑になって今刑務所はまさに変わってきましたが、更に変わろうとしています。大臣、法務省で検討してください。
○国務大臣(鈴木馨祐君)
御指摘のように、拘禁刑、これから導入ということで、私どもとしてもそうした様々な転換点にあると考えております。国際的な潮流ということも承知をしております。
まさにそういった中で、一般論として、受刑者の社会復帰にとって、社会のルールを決めることに参画をする、あるいはルールを守るということ、これを学ぶ、これは極めて重要だと思います。
ただやはり、これは繰り返しになって大変申し訳ありませんけれども、やはりこれは様々な観点を踏まえて議論をしていくことだと思います。まさにそこは、そういったことがもろ手を挙げて全ての方が賛成をしているのかというと、そういう状況でもまだない状況の中でありますので、まさにそこは国民の間での議論ということもこれ極めて大事になってくると思います。
そうした中で、是非これは各党各会派、この立法府の中でしっかりとこれ議論を深めていただく、そういったことを私どもとしてはしっかりと見てまいりたいと考えております。
○福島みずほ君
裁判で争われ、最高裁で係属しているんです。ですから、それは、国民各層のいろんな意見があり、政党がじゃないでしょう、法務省の中で場を設けて議論をしてくださいよ。君、さんを付けるだけでも変わるんですよ。人間の尊厳の問題じゃないですか。社会に帰ってくるんですよ。このことで受刑者に選挙権をちゃんと付与すべきであると。国民投票で認めるのは一歩です。これは認めるべきだと強く申し上げます。是非、やっぱりそれは根本的な価値の問題ですから、法務省でこれを議論してくださるよう強く申し上げます。
二〇〇二年に名古屋刑務所事件が起き、二〇〇三年十二月、行刑改革会議提言がありました。改めてこれを読みました。受刑者の人権を保障し、刑務官の労働条件を向上させる、受刑者の社会復帰と犯罪の防止、「国民に理解され、支えられる刑務所へ」というのが提言の題です。二〇〇六年、監獄法が改正をされました。森山眞弓大臣が、名古屋刑務所を受けて、大臣の首を懸けて刑務所改革をし、そして監獄法の改正をやったということ、とてもそれは本当に法務省が頑張ったんだと思います。当時、総務課長は後に検事総長となる林真琴さんで、今の官房長やいろんな人たちも当時若手でしたが、とても頑張ったわけです。その延長線上に六月一日の拘禁刑の一本化があります。それで、いろんな処遇、単に懲らしめるんじゃなくて、一人一人に合わせた、少年院などの手法も加味してやっていくということを本当にやっていただきたいんですが。
私は、実は映画とか見るの大好きで、「シンシン/SING SING」という映画を最近見ました。ニューヨークでまさに演劇をやる、そうすると、ギャングだった人間がもうすごくどんどん上手になって、今俳優さんになっているんですね。「塀の中のジュリアス・シーザー」、イタリアの刑務所は、実際、劇場があり、カーペットを敷き、外部からも人を呼び、「ジュリアス・シーザー」とかをやっているわけですね。それは、人間のプライドや、それから、やっぱり自分の罪を見直すじゃないけど、物すごく人間にとってやりがいや変わっていくという契機になる。グリーンフィンガー、ガーデニングのコンクールに出る、それはイギリス。韓国の映画だと「ハーモニー」とか、女性たちが合唱コンクールに出る。やっぱりそういうので変わっていくんですよね。
是非、「シンシン/SING SING」の映画を見て、日本でも少年院でやっていると聞いておりますが、是非、演劇、そういうのをやったらいいんじゃないか。いかがでしょうか。
○政府参考人(小山定明君)
恐れ入ります。刑事施設の中には、これまでも個々の受刑者や各施設の実情に応じまして、クラブ活動といたしまして絵画や音楽などの表現活動を取り入れているところもございますが、御指摘のような演劇プログラムのようなものは現在のところ実施していないと承知しております。
拘禁刑下におきましては、より一層個々の受刑者の特性に応じた矯正処遇を実施することとしておりますことから、例えば読書会といったようなものを取り入れて、いろいろなその本の感想を受刑者同士で言い合ったりといったようなことも始めてきておりますし、また、受刑者に、少年院でこれまで実施してまいりました映像表現コンクールというものに本年度から成人部門を設けまして、受刑者が参加する取組を試行的ではございますが開始することとしております。
このような取組を含めまして、今後とも、様々な知見を得ながら、拘禁刑化における矯正処遇等の充実を図ってまいりたいと考えております。
○福島みずほ君
演劇は、やっぱり自分を見直す、あるいは別の人間になる、あるいは演ずることですごくやっぱり達成感もある。それから、チームワークでやらないとやれないとか、物すごくいろんな要素があると思うんですね。
是非そういうことをやる、その中から俳優さんが将来出てきてもすばらしいじゃないですか。私は、是非そういうことを、少年院ではやっていらっしゃるというふうに聞いたこともありますが、やってくださるよう、そして拘禁刑に伴うまさに矯正、刑務所がもっともっと本当に社会復帰の場所になるように精いっぱい本当に応援をしていきたいと思います。頑張ってください。
選択的夫婦別姓についてお聞きをします。
大臣、選択的夫婦別姓を実現することのメリットにどういうものがあると思われますか。
○国務大臣(鈴木馨祐君)
メリット、デメリットということ、メリットということでありますけれども。
この夫婦別氏、この制度望まれる方々の中で、やはり氏を含む氏名、これは個人のアイデンティティーに関わるということ、そういった価値であるということ、あるいは、夫婦、親子の氏が異なっていても夫婦を中心とする家族の一体感、きずな、これ、そういったデメリットはないという、そういった御意見、さらには、現行法の下で旧姓の通称使用の拡大ではなかなか全てが解消されるわけではない社会生活上の不利益、この解消につながる等々、そういった御指摘があるということを承知をしております。
○福島みずほ君
だったら、何でやらないんでしょうか。
大臣、私は、夫婦別姓を望み、ずっと事実婚ですから、パートナー、夫と娘と名前が違います。姓が違うんです。でも、ずっと本当に仲よくやっています。私の周りには別姓を待ち望んでいる人たちがたくさんいます。
別姓になると家族壊れると思われます。
○国務大臣(鈴木馨祐君)
まさに、そこは一概には申し上げられないことではないかと思っております。
○福島みずほ君
壊れないですよ。夫婦同姓で仲の悪いカップルなんて、弁護士としてたくさん見てきました。同姓でも別姓でも、仲いい人もいれば悪い人もいる。同姓、もう家庭裁判所は同姓の離婚カップルばっかりですよね。
ですから、まあ大臣笑っていらっしゃいますが、そうなんですよ。それは実質的な話であって、いい人もいれば悪い人もいる。それは別姓と同姓と関係がないんです。
夫婦別姓で、子供……(発言する者あり)はい。夫婦別姓で、まさに戸籍がなくなるというような議論がありますが、法制審議会が出しているように全く変わらない。いかがですか。
○国務大臣(鈴木馨祐君)
私どもとして、以前法制試案ということで検討いたしましたが、そこで戸籍がなくなるということではないと承知をしております。
○福島みずほ君
子供がかわいそうなんでしょうか。
○国務大臣(鈴木馨祐君)
そこもそれぞれいろいろなケースがありますので、そこも一概には申し上げられないことかと思います。
○福島みずほ君
子供、かわいそうなんということないですよ。それは、ちゃんと別姓、もし別姓制度が法律化されて、そういうのも一つの選択肢となれば、もっと子供たち生きやすくなりますよ、本当に。
離婚が増えるという意見がありますが、そう思われますか。
○国務大臣(鈴木馨祐君)
そこも個々の様々なケースによると思いますので、一概には言えないことかと思います。
○福島みずほ君
離婚、増えないですよ。私、もし同姓で無理していたらもうとっくの昔に別れたかもしれないので、別姓でよかったです。
それで、むしろ、今若い人たち、私の周りにも、夫婦別姓制度が選択的に認められたら結婚するという人たちがたくさんいるんですよ。結婚が増えますよ。というか、人が結婚することを阻んでいるんですよ。何で人が幸せになることを法律が阻むんですか。いろんな意見があると言うけれど、何で人が幸せになることを邪魔するんですか。いろんな幸せがあっていいじゃないですか。日本、全ての女と結婚するわけじゃないんですよ。あなたは同姓でいい、別姓の選択肢もある。
それで、同性婚もちょっと似たところがあると思います。誰を好きになったかによって結婚届が出せない。大臣、夫婦、ごめんなさい、同性婚を認めることのメリット、どう思われますか。
○国務大臣(鈴木馨祐君)
まさに同性婚につきましてということでありますけれども、まさにこれが認められないことで負担を感じている、そういった方がいらっしゃるという声、ここについては十分承知をしているところであります。
ただ、その一方で、この同性婚制度の問題、これは親族の範囲であったり、あるいはそこに含まれる方々の間にどのような権利義務関係を認めるかといった国民生活の基本に関わるものということでもありますので、国民一人一人の家族観と密接に関わると認識をしておりまして、これまさに、国民各層の御意見、これ様々ございますので、こうした国会における議論の状況等々も含めて我々としては注視をしていきたいと考えております。
○福島みずほ君
今大臣は親族に関係あるとおっしゃったけれど、意味が不明です。つまり、二人が結婚して法定相続人になるということはありますね。でも、親族にって関係ないじゃないですか。だって、Aという人とBという人、異性愛で結婚して親族に関係があるって関係ないじゃないですか。親族の了解なんか要らないですよ、どこも。
○政府参考人(竹内努君)
お答えいたします。
今委員御指摘のところでございますが、同性婚制度を設けた場合の権利義務関係についてでありますけれども、特にやっぱり親子関係の在り方については十分な検討が必要となるのではないかというふうに考えておるところでございます。
すなわち、女性同士のカップルの場合に、例えば一方の女性が出産をしたというケースですと、その子供について、他方の女性が子の親となるのか、あるいは、親となるにしても、女性たる父となるのか、あるいはもう一人の女性たる母となるのか、それとも全く新しい概念をつくり出す必要があるのかといった点についても検討する必要があるのではないかと考えているところでございます。
○福島みずほ君
じゃ、検討すればいいじゃないですか。諸外国は全部それ問題クリアしていますよ。同性婚認めて、そして検討したらいいじゃないですか。なぜ全ての検討が終わらない限り結婚届出せないんですか。
法定相続になれない、税制上の特典がない、赤の他人、配偶者ビザが出ない、もう本当に大変なんですよ。選択的夫婦別姓と同性婚、私は何で人が幸せになることを阻むのかが分からないんです。幸せになる人が増えるだけなんですよ。それを全部議論しない限りあなたの幸せは実現しません、法制度が阻んでいるんですよ。
大臣、大臣は実は分かっていらっしゃると思います。人が幸せになることを応援するのが法制度でしょう。でも、今、日本でこれ阻んでいるんですよ。おかしくないですか。
○国務大臣(鈴木馨祐君)
委員御指摘の御趣旨、ここは私も私なりに理解をしているつもりであります。
その一方で、それぞれの制度について極めて真剣な懸念を持っている、そういった方がいるのも事実であります。そういった中でありますから、ここについては是非立法府の中でしっかりと議論を深めていただきたいと思いますし、これは最終的には国民の皆様方が決めるということかと思います。

○福島みずほ君
さっき、様々な懸念は事実ですかと言って、大臣全て違うと答えたじゃないですか。
つまり、懸念があったら人が幸せになることを阻むんですか。あなたの幸せを、夫婦同姓になる人を邪魔したりしません。夫婦同姓になることに懸念があるなんて言いません。夫婦同姓に関して邪魔しないですよ。にもかかわらず、別姓になることを、同性婚になることを何で懸念があると言って邪魔するんですか。分からない。ここにいる全ての皆さんにも申し上げたい。分からないですよ。いろんな家族観、いろんな家族観、それがあることは理解します。あなたの家族観は尊重します。しかし、違う、違う選択肢があることを認めないということが問題だと思うんです。あなたの家族観は認めます。だけど、選択制で別姓があることや同性婚で結婚できることを認めるべきです。法律はそれであるべきだと、私は本当にそう思います。
女が困っている。女ばっかりではない。でも、困っていると叫んでいる。同性愛の人たちが何とかしてくれと叫んでいる。何でそれを無視して、おまえたちの幸せは全部検討するまで実現しない、懸念があると言うんですか。懸念は全部さっき大臣否定したじゃないですか。おかしい、そう思います。
何で人の幸せになるのを邪魔するのか。こんな国会でいいんですか。私は本当に怒っています。本当に怒っています。この日本、沈没しますよ。人が結婚することを、幸せになることを邪魔するような国会だったら、この日本、沈没しますよ。変えましょうよ。それを強く言いたいと思います。
共同親権について一言申し上げます。
この共同親権についてガイドライン案が今作られていて、この参議院の法務委員会の中で、まさに、例えば高葛藤事案に関しては、単独で、もうそれは共同親権が難しいというふうに小泉法務大臣はおっしゃいました。そのことを生かしてほしい。高葛藤事案でとても合意がないというような場合には単独親権ということでガイドライン作っていただくということでよろしいですね。
それからもう一つ、急迫の場合に関して、例えば、いろんな単独で親権ができるか、子供を連れて出れるかというときに、この急迫の事情に関しては時間の概念ではないというふうに大臣は当時おっしゃいました。時間の概念でもない。やっぱり、いろいろ準備して、離婚の準備もして、それから子供を連れて出ようという人もいると思います。
この二点について、ガイドラインにしっかり書かれるということの確認をさせてください。
○政府参考人(竹内努君)
お答えいたします。
委員御指摘のQアンドA形式の解説資料でございますが、現在、この内容につきましては、関係府省庁等との間で検討、調整を行っているところでございまして、現時点で具体的にお答えすることは困難ではございます。
いずれにせよ、民法改正法に関する周知、広報の重要性は大変認識をしているところでもありますので、委員の問題意識も踏まえまして、スピード感を持って施行準備に取り組んでまいりたいと考えております。
○福島みずほ君
しっかり盛り込まれるということでよろしいんですね。
○政府参考人(竹内努君)
今、解説資料の内容については、まさに議論中でございますので、確定的なお答えをすることは困難ではございますが、委員の問題意識も踏まえて取り組んでいきたいと考えております。
○福島みずほ君
この参議院の法務委員会で、とりわけいろんな確認事項を取りました。さっき言ったことがしっかりガイドラインに盛り込まれるというふうに理解をいたしました。是非、参議院の法務委員会で獲得したものがちゃんとガイドラインに盛り込まれるよう心からお願いをして、質問を終わります。
大臣、選択的夫婦別姓、同性婚、実現しましょうよ。あなたのポリシーでもあるじゃないですか。よろしくお願いします。
終わります。
※本議事録は未定稿です。