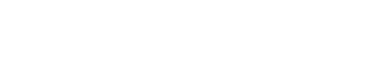○福島みずほ君
立憲・社民・無所属共同会派、社民党の福島みずほです。
まず初めに、非正規公務員問題についてお聞きをいたします。
自治体によっては半分が非正規公務員、国家公務員も非正規が多いです。国家公務員ですが、ハローワークの常勤職員及び相談員数でいえば、二〇二四年、相談員数、非常勤職員は六四・三%と非常に高いんです。非正規の人たちがどれだけ通常業務というか、働いているかというふうに思います。
それで、妊娠などによって雇い止めが発生しているわけですが、会計年度任用職員、それから国家公務員の場合ですが、声があることを知っていますか。
○副大臣(冨樫博之君)
本年一月に、総務省などの職員と関係団体の方々との間で会計年度任用職員をめぐる問題について意見交換をさせていただきました。その際に、産前産後休暇や育児休業の取得を理由に雇い止めに遭ったと訴える会計年度任用職員の声があったことについては承知しております。
○福島みずほ君
是非対応を取っていただきたい。ヴォイセズやいろんな当事者団体の人たちと実際行政交渉をしたり、私も直接話を聞いています。ちょっと聞いてください。
当事者。私は、中国地方の自治体で働く会計年度任用職員の女性です。これまで通算約六年間、同じ町の二つの部署で臨時職員、会計年度任用職員として働いてきました。今年三月に出産予定のため、昨年の秋に、三月に出産予定なので産休、育休を取得したいと希望を伝えた。すると、会計年度職員の契約は四月から三月末、三月に出産して四月時点で休むことになる人は契約更新できない、また働きたいのであれば一から面接を受ける必要があると説明をされたというのがあるんですね。結局、雇い止めになったという人です。
それから、ほかにも当事者の声がたくさんあります。三年前の話です、当事者の人。会計年度任用職員として二年勤務していましたが、妊娠発覚とともに職場に相談し、今後のことについて確認したところ、産休、育休を取得中の人を再度の任用をすることは周りに説明できない旨回答をされました。後日、ある省のマニュアルを確認し、抗議しました。マタハラに当たる旨も指摘すると、人事権のある上役と再度話合いをすることになりました。ずっとこの人は交渉し、ただ、最後、非常にこじれてしまって、育休は取得することができるけれども、かなりこじれたので育休明けの採用面接では不採用になったというのがあります。
また、当事者。妊娠が分かったら契約更新しないと言われ、一年の任期で終わった。あるいは、国家公務員ですが、あなたの勤務態度は良いと言われたんですが、四月上旬に出産をする予定であると。去年、去年というか、それ言ったら、あなたの勤務成績はいいと、ただ、妊娠の時期が半年早いか半年遅ければ良かったのにと、こう言われて、公募を受けなくちゃいけないということなど、本当にたくさんのいわゆるマタニティーハラスメントじゃないか、あるいは、妊娠したら、いや、契約更新できませんという雇い止めのケースがたくさん発生しています。
それで、真面目に働いているのに一年ごとに更新がある、これで実は雇い止めに遭うんですね。どのような改善策があり得るでしょうか。

○副大臣(冨樫博之君)
産休や育休を理由とする不利益な取扱いは、地方公務員法第十三条や地方公務員育児休業法第九条により制度上禁止されております。
この取扱いについては会計年度任用職員であっても同じであり、各自治体に対して、QアンドAや地方公務員両立支援パスポートに明記することなどを通じて周知を図ってまいりました。
総務省としては、各自治体において育児休業の適正な運用が行われるよう、今後とも情報提供や助言をしっかりと行ってまいります。
○福島みずほ君
副大臣はそうおっしゃいましたが、実際マタハラが起きているんですね。それから、産休をどれだけ取れたかという実態は人事院も総務省も取っていないということで、分からないんですね。しかも、一年間ですから、どこかで妊娠して出産するときに掛かると、そこで雇い止めに遭ってしまうと。
本当に、これ改善策取らないと、絵に描いた餅で、妊娠、出産して働き続けられますよというのはできないんですよ。正規であれば子供を産んで産休、育休取れるけれども、会計年度職員あるいは非正規だとこれができないということで、この改善、本当に真面目に考えてほしい。実態が取れてないんですよ。どうですか。つまり、一年ごとの契約更新、それから公募があることで、実際はマタハラの制度化ができて、制度化みたいなことが起きているんですよ。いかがでしょうか。
○政府参考人(小池信之君)
お答えいたします。
実態の調査をすべきという御質問でございますけれども、育児休業取得者など特定の属性の人が任用されたかどうかという点につきましては、各自治体の具体的な任用に関わることでもございますので、総務省で調査することは考えていないところでございます。
○福島みずほ君
いや、今の回答はひどいですよ。もちろん地方自治の本旨はあります。しかし、取れてないんですよ。当事者の方から、いや、私は、妊娠したと言われたら、例えば十月に、早めに言わなきゃ、妊娠したと言ったら、来年三月の更新はありませんと言われちゃうわけですよ。これ、変えてもらいたい。何か対策取らないと。
あるいは、さっきもハローワークの人の非正規公務員割合を言いましたが、本当はずっとみんな働いているんですよ。一年ごとの契約更新でできるようなことじゃなくて、みんな真面目に働いているんです。だけど、妊娠を告げた途端に更新がしませんよともう秋の段階で言われる。これが実態なんです。対策打つべきじゃないですか。
○政府参考人(小池信之君)
先ほど副大臣から御答弁しましたとおり、産休や育休を理由とする不利益な取扱いは禁止をされておりまして、その点については私ども総務省から各自治体に対して何度も周知をしているところでございますので、各自治体においてそういう運用をしていただきたいと考えております。
○福島みずほ君
セクハラ、パワハラについて声を上げにくい実態は御存じでしょうか。
○副大臣(冨樫博之君)
総務省では、自治体におけるハラスメントについて、個別具体的な発生事案や件数を承知しているわけではありませんが、今年度、初めて、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントを含む各種ハラスメントに関する実態把握のために、会計年度任用職員を含む二万人の自治体職員に対してアンケート調査を実施しております。この中では、例えばハラスメントを受けた経験の有無や、受けた場合における被害の内容などについて調査しているところです。調査結果については現在集計中でありまして、取りまとめが終わり次第、公表したいと考えております。
以上です。
○福島みずほ君
人事院、いかがですか。
○政府参考人(荒竹宏之君)
お答えいたします。
一般職の国家公務員の非常勤職員のセクシュアルハラスメントやパワーハラスメントについては、令和五年度にハラスメント相談の実情を把握するために職員アンケートを行っており、この中で対象として抽出した非常勤職員一千人のうち、回答のあった六百四人中、ハラスメントを受けたと感じたことがあると回答した職員が約二割、百二十三人となっておりました。このハラスメントを受けたと感じたことがあると回答した職員に対し、受けたと感じたことのあるハラスメント内容を尋ねたところ、パワーハラスメント関連では暴言が三九・〇%、セクシュアルハラスメント関連では性的な発言が二一・一%などとなっているところでございます。
○福島みずほ君
今ので、回答があった人のうち二割がパワハラ、セクハラがあったというすごい切実な答えですよね。それは匿名のアンケートですから声を上げられるけれど、普通は顔を出し、名前を出しできないんですよ。次の更新のときに落とされるんじゃないかというふうに思って声を上げられない。
そして、公募なんですが、例えば、国家公務員も地方公務員も公募をやると、そして、予算の関係上、三人を二人にする、三人を一人にする。そうしたときに、例えばパワハラ、セクハラを公益通報した人を落とす手段になるとか、この人は盾突いたとか文句言ったとか、あるいはマタハラの場合もあります。公募が実際は、そのパワハラ、マタハラ、セクハラの問題を、落とす手段になっている、声を上げた人を落とす手段になっているという現状があるのですが、このことはいかがでしょうか。
○副大臣(冨樫博之君)
各種ハラスメントの申出については、関係法律及び厚生労働大臣指針において、労働者が事業主にハラスメントの相談を行ったことなどを理由とする不利益取扱いの禁止が定められています。
総務省としては、関係法律等を踏まえ必要な措置を講ずるよう、これまでも自治体に対して助言を行ってまいりました。その上で、会計年度任用職員の任用に当たっては、地方公務員法に定める平等取扱いの原則や成績主義を踏まえ、できる限り広く公募を行うことが望ましいと考えております。
いずれにしても、会計年度任用職員の適切な任用が確保されるよう、引き続き必要な対応をしてまいります。
○福島みずほ君
さっき人事院も、回答あった人の二割がセクハラ、パワハラがあったというふうに回答されたじゃないですか。実際、深刻、切実なんですよ。正規の人もだけれど、ましてや声を上げにくいと。ですから、パワハラ、セクハラがあった場合はそれをきちっと取り上げますという副大臣の答弁は、実は現実と合っていないんですよね。マタニティーハラスメントが起きている、産休、育休取れない、パワハラやセクハラに遭っても声を上げられない、これが多くの人の現実ですよ。
私は、友人たちにも一年ごとに働くという人いますが、自分が更新されるかどうか。例えば、子供を育てている、これ職を失うわけにはいかない。今度子供が生まれる、四月に生まれる、働き続けたい、でも自分が更新されるかどうか分からない。公募をやるぞと突然言われるという中で落とされたりしているんですね、あるいは契約更新拒絶に遭っているんですよ。これは本当に解決をしないといけないというふうに思います。
副大臣、自分の言葉でというか、どうしたらいいのか、役人の方でも結構です、こういうことをやっていくというのがあれば、人事院あるいは総務省、あるいは、いかがですか。

○政府参考人(小池信之君)
先ほど副大臣が答弁申し上げましたとおり、この厚生労働指針におきまして、労働者が事業主にハラスメントの相談を行ったことなどを理由とする不利益な取扱いは禁止をされているところでございます。
現場のお話を今委員からいろいろお伺いしておりますけれども、現場におきましてこういったことがないように、起こらないようにというのは総務省としてもそのように思っておりますので、引き続き地方自治体に対しまして助言を行ってまいりたいと考えております。
○福島みずほ君
今日の問題提起は、現場で起きていることが、実は、一年ごとの契約更新であったり公募があるために、その公募が落とす手段になる、あるいは雇い止めの手段になる、だから制度そのものがマタハラの制度化ではないかということを強く思っているんです。私は、ずうっと必要な仕事をずうっと真面目にやってきているんだったら期間の定めのないものにするとか、いろんなことをもうやっていかないと駄目だと思っています。
公共サービスが弱体化していく、優秀な人材が来ない、辞めていくことをどう考えますか、人事院、総務省。
○副大臣(冨樫博之君)
複雑化、多様化する行政需要に対応するため、常勤職員に加え非常勤職員も地方行政の重要な担い手となっていると認識をしております。
会計年度任用職員として任用する場合には、制度上、一会計年度を超えない範囲で任用する必要があり、その任用に当たっては地方公務員法に定める平等取扱いの原則や成績主義を踏まえ、できる限り広く公募を行うことが望ましいと考えております。ただし、客観的な能力の実証を得た再度の任用や選考において、前の任期における勤務実績を考慮することも可能であることなどについて自治体に対してこれまでも通知をしております。
また、昨年の六月に、国のいわゆる公募三年ルールが廃止されたことを受けて、総務省においても自治体に対しその旨を通知しております。
いずれにしても、会計年度任用職員が十分力を発揮できるよう、今後とも環境や制度の整備に取り組んでまいります。
○政府参考人(堀内斉君)
お答え申し上げます。
期間業務職員のポストは、相当の期間任用される職員を就けるべき官職以外の官職とされておりまして、一会計年度に限って臨時的に置かれるものとされております。
総務副大臣から言及ございましたように、かつては公募によらない再度の採用の上限回数、いわゆる公募三年要件と認識されていたものがございましたが、これにつきましては、期間業務職員としての適性を有する人材が三年を区切りに公務外に流出するなどの弊害が生じていたことに鑑みまして、昨年六月、それぞれの職場において人材確保の実情に応じた方法で柔軟に採用を行うことが可能となるよう上限回数を削除いたしました。
人事院といたしましては、行政サービスの提供を支える有為な人材の確保に向け、各府省が円滑に運用できるよう引き続き支援してまいりたいと考えております。
○福島みずほ君
若干改善はされてきているのはもちろん承知しています。でも、現場の声がこれなんですよ。物すごく何とかしなくちゃと思い、一年ごとの更新、それから公募については根本的に見直すべきだと申し上げます。
これは、国家公務員の非常勤の人から言われたんですが、非常にストレスを感じ、今年あったストレスチェックで高ストレスとの結果が出て、医師の面談を受けたと。医師より早急な職場内の人間関係の改善が必要と指示が出たと。しかし、医師の指示が出たけれども、医師の指示が出た場合、職場で取り組むことになっているけれども、何にも面談や改善が行われない。こういう実態、御存じでしょうか、あるいはどう思われますか。
○政府参考人(荒竹宏之君)
お答えいたします。
人事院規則において、各省各庁の長は、ストレスチェックにより心理的な負担の程度が高いと評価された希望する職員に対して面接指導を行う必要があります。その上で、医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、当該職員の健康を保持するための措置を講じなければならないこととされているところであります。
こうした規則の定めに基づき、各府省において実情に応じて適切に判断されるべきものと認識しております。
○福島みずほ君
ちゃんと行われるようにと思います。
こういう質問をしたのは、やっぱり物すごくストレスを感じて、自分は契約更新されないんじゃないか、あるいは公募で、例えば三人非常勤いても、二人になるときに私は落とされるんじゃないかとか、物すごいストレスを感じながら働いているわけですね。こういう状況で私はいい仕事もできないし、本当はずっと必要な仕事だと思っています。ですから、この会計年度任用職員制度と、それから国家公務員の非正規の問題に関しては根本的な解決が実は必要であると思っています。もちろん、定員法だったりいろんなレベルの問題がありますが、是非、現場の本当に苦しい、物すごい深刻な実態を知って、改善をしてほしいというふうに思います。
次に、全国一律最低賃金千五百円についてですが、政府は二〇二〇年代までに最低賃金を千五百円と言っています。できる限り早く千五百円を実現すべきでないかということなんですが、今日は地方創生の委員会ですから、全国一律にすべきではないかという観点をお聞きをいたします。
というのは、最低賃金は全国で、御存じ、かなり格差があります。そうすると、狭い国ですから人口移動が起きる、つまり最低賃金の全国格差が人口の移動、東京都、大都市への流入につながっているという面があります。ですから、全国一律最低賃金千五百円、これを早期に実現していただきたい。いかがでしょうか。
○政府参考人(田中仁志君)
お答えいたします。
最低賃金についてのお尋ねでございます。
最低賃金の地域間格差の是正に取り組んでいくことは、政府としても大変重要なことであるというふうに感じております。平成六年度におきまして、各地方最低賃金審議会で地域間格差是正の観点も含めて御議論をいただいた結果、地域間格差につきましては、地域別の最低賃金の最高額に対する最低額の比率、これが八一・八%ということでございまして、十年連続で改善をしてきたところでございます。引き続き、地域間格差の是正には取り組んでまいりたいというふうに思っております。
他方、直ちに全国一律の最低賃金とすることにつきましては、地域の経済状況等が異なる中で、引上げ幅は地方ほど高くならざるを得ず、特に地方の中小企業の負担は大きくなるということには留意をする必要があるんじゃないかというふうに考えております。慎重に考えていくべきではないかというふうに認識をしております。
○福島みずほ君
地域別の最低賃金があるのは、アメリカやオーストラリアなど広い国ですよね。日本のように狭い国だと高い賃金のところを求めて人口が移動するので、もし地方にいて働いてもらいたいと思ったら、全国一律最低賃金の方がいいんですよ。徳島など、むしろ中小企業自体を応援して最賃を上げようという努力をしているところもあります。やっぱりこれは全国一律最低賃金。これは、地方は車も掛かりますし、コンビニの値段は全国一緒です。確かに大変ですよね、今九百円台が千五百円となると、高くなりますから。でも、しかし、全国一律最低賃金という意味は、これ実現しなければならないということを強く申し上げます。
それから、地方からの人口流出とジェンダー問題についてお聞きをいたします。
様々なアンケート、これは国土交通省のですが、東京圏流入者が移住することを選択した背景となった地元の事情で、これは男女別に見ると、男性は仕事や進学先関係の割合が高いのに、女性は人間関係やコミュニティーに閉塞感がある、地域の文化や風習が肌に合わないとかの割合が高いのです。
これ、やっぱりジェンダーギャップ、ジェンダーの問題がやはり人口流入を起こしているとすれば、地方は地方という問題とジェンダーの問題と二つの問題を抱えるということに、もちろん東京も問題がありますが、この点についていかがでしょうか。

○副大臣(鳩山二郎君)
御質問ありがとうございます。お答えをいたします。
これまでの地方創生の取組により様々な成果が生まれた一方で、東京圏への一極集中の流れは止まっておらず、その主な要因は、若者の東京圏への転入超過に加え、特に男性よりも女性の方が多く転入する傾向にあると認識をしております。
地方からの女性、若者の流出の原因としては、男女間、地域間の賃金格差やアイコンシャスバイアス、若者や女性から見ていい仕事、魅力的な職場、人生を過ごす上での心地よさ、楽しさが地方に足りないなど、問題の根源にリーチできなかったのではないかなどの御指摘が、御指摘されているものと認識をしております。
こうした議論を踏まえ、地方創生二・〇においては、若者、女性にも選ばれる地方をつくることを主眼とすることが重要であると考えております。
○福島みずほ君
男女共同参画局、これに向けての政策、お願いいたします。
○政府参考人(小八木大成君)
お答え申し上げます。
内閣府男女共同参画局におきましては、女性版骨太方針二〇二四及び第五次男女共同参画基本計画に基づきまして、各地域の企業における女性活躍推進に係る好事例の周知啓発、中小企業における女性活躍の推進への支援、男性の育児休業の取得促進に向けた経営層や管理職も含めた周知啓発、地方公共団体における地域の実情に応じた取組への支援、またその各首長のコミットメントの強化の促進など、関係省庁と連携しながら、地域における女性活躍、男女共同参画の担い手を育成し、女性が働きやすく魅力ある職場づくりに取り組んでいるところでございます。
また、魅力ある職場づくりの一環としまして、女性の起業への支援に取り組むとともに、固定的な性別役割分担意識やアンコンシャスバイアスの解消に向けて、情報発信にも取り組んでおります。
また、地域の男女共同参画の社会の形成のその拠点となりますセンター、男女共同参画センター、こちらの人材育成ですとか研修ですとか、それからその情報の分析、状況の分析ですね、こういったところのその力を強化するというふうな趣旨で、NWEC、女性、国立女性教育会館ですね、こちらのその機能強化についても取り組んでいるところでございます。
引き続き、女性が働きやすく暮らしやすい地方とするための取組を進めていきたいと思っております。
○福島みずほ君
今、たまたまNWECとおっしゃいましたが、NWECが宿泊棟や研修棟を撤去しようとしているのは問題で、一億、二億、三億の修繕費を削除、けちらないで、是非、唯一のナショナルセンターとして、もっともっと研修も宿泊もできるような場所で頑張っていただきたいと思いますし、男女共同参画の役割はとても大きいと思います。
それで、LGBTQやジェンダーもそうなんですが、早く結婚しろとか、まだ結婚しないのかとか、何で結婚しないのかとか、子供を産めとか、いろいろ言われる。地元に帰ると、お正月とか帰ると、男の人たちはお酒を飲んでいて、女の人たちが台所で立ち働いているみたいなと、ああ、もう無理、無理、無理というように若い人だと思うというようなことや、たくさんの話も聞きます。是非、様々なことを変える必要があると思います。
都道府県別ジェンダーギャップ、あなたの町の男女平等度はという本があるのですが、大変面白くて、一つ目は、どの分野も上位がばらばらで、決して東京一強ではなく、地方の方が進んでいる分野がある。二つ目は、指標によっては男女格差だけでなく地域格差が歴然と存在し、地方の女性は性差と地域の二重の格差による影響を受けている。でも、非常に頑張れば指標は変えられるというので、例えば行政の男女格差が最も小さいのは鳥取。二〇二二年から三年連続一位、元知事の片山善博さんが三十年以上前に、女性にお茶くみだけをさせないとの考えから人事制度を全面的に見直し、男女とも平等に主要ポストを経験できるようにするなど、先駆的な取組を始めたことがきっかけである。それから、例えば熊本。熊本は、二〇一六年の熊本地震で避難所に授乳室がなく困った女性がいたなど、困難を把握したのをきっかけに、条例改正で防災委員を増員、熊本地震の際に避難所運営をしたNPO法人の代表ら複数の女性を選び、一〇%台だった女性割合を二三年には三〇%超まで高めた。
つまり、地方が非常に努力をしたり変わることで随分変わるという例もあります。是非、そのジェンダー平等をあらゆるところで実現していく努力というのは本当に必要だと思います。
それで、せっかく地方創生のこの特別委員会なので、私自身は宮崎県出身で、九州の出身です。幼稚園から大学まで、国公立大学だったので、同級生の中には農業をやっている家の人、子供や、いろんな子供がいました。私は社会民主主義者で、新自由主義に反対しているんですね。大都会の大企業が潤えば、トリクルダウンして地方も潤えるなんて全く思えない。地方にはそれぞれの良さもあって、新自由主義、大企業の利潤さえ追求すればうまくいく経済、社会ではあり得ないと思っているんです。だから、どの地域でも、どこでも子供は、そして誰でもやっぱり公平に、まさにトランプ大統領が今やめると言っているダイバーシティー、D、E、エクイティー、それからインクルージョン、Iですね、DEIこそもっともっとやっていかなければならないと思っています。
ところで、何で地方が疲弊していくのか、それはやっぱり私は新自由主義のせいだと思っています。国鉄を分割・民営化し、国立、公立病院、公的病院の再編、統廃合をやり、水道法の民営化法を作り、どんどん民営化をし、そして農業予算は、軍事予算が八兆七千億円の予算案なのに二兆円台です。三分の一でしかありません。地方が疲弊するのは当たり前だと思います。
副大臣、これ通告しておりませんが、根本的にやっぱり地方が何でこんなに疲弊しているのか、農業を応援しないし、公立病院潰すし、学校統廃合するし、役所はもう本当に合併で潰していくし、交通はないし、国鉄もないし、こういう状況で本当に疲弊するのは当然だと思います。大臣、いかがですか。
○副大臣(鳩山二郎君)
御質問ありがとうございます。
私もかつて三万三千人の小さい自治体の市長をさせていただいていたので、地方都市の厳しさは痛感をしておりまして、賛同する部分も多々あるわけでありますが、私は地方創生担当の副大臣としてこの場所で立っておりますので、地方創生に関して答弁をさせていただきます。
昨年末に取りまとめた地方創生二・〇の基本的な考え方においては、五本の柱の一つに、安心して働き、暮らせる地方の生活環境の創生を掲げ、その中で、若者、女性にも選ばれる地方として、地域間、男女間の賃金格差の是正、非正規雇用の正規化の推進、男性の育児休業の推進などの取組方向を示したところであります。
先日、長野県伊那市で開催された有識者会議においては、高齢者や障害をお持ちの方、子育て中のお母さんなど、様々な方々が地域住民と一緒に交流する集いの場が形成され、高齢者が赤ちゃんのお世話をするなど、それぞれの方にとって暮らしやすいコミュニティーづくりが実践されているという話があったと報告を受けております。
こうした現場の取組も参考にしながら、若者、女性が働きやすく、暮らしやすい地域づくりに向けた議論を深め、施策を具体化してまいりたいと思います。
○委員長(山田太郎君)
時間が来ていますので、おまとめください。
○福島みずほ君
ありがとうございました。終わります。
※本議事録は未定稿です。
●質疑の動画(字幕付き)は下記からご覧になれます●