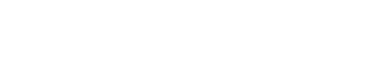ACTIVITY BLOG活動ブログ
2025.4.10 参議院 法務委員会での質疑 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)
○福島みずほ君
立憲・社民・無所属共同会派、社民党の福島みずほです。
職員の数、増減についてお聞きをいたします。
概算要求で四十三名増員を最高裁の事務官について最高裁はしておりました。四十三名要求した理由は何ですか。
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君)
お答えいたします。
裁判所といたしましては、今回、裁判の、家庭裁判所の審理運営を検討していく、あるいはデジタル化を進めていくといったような観点から、家裁調査官の増員あるいは事務官の増員というものもお願いをしているところでございます。また、いわゆるワーク・ライフ・バランスに関する増員もお願いしているというところでございます。
一方で、いわゆる技能労務職員を、がアウトソーシングしていくというような過程の中で、退職された後、その職員を、あっ、不補充にするというような形で事務の合理化を進めていくといったようなことを含め、裁判所の事務の合理化に伴う人員の合理化も進めているということでございます。
そして、その差引きをした結果が今回の減員ということになっているということで御理解をいただきたいと思います。
○福島みずほ君
裁判所が四十三名概算要求で要求したということは、やっぱりそれだけ必要だと考えたからじゃないですか。これが、九名しか事務官が認められなかった。これは非常にがっかり、問題があるんじゃないですか。
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君)
お答えいたします。
概算要求の段階におきましては四十三人の増員が必要というふうに考えて増員の要求をしたということは、御指摘のとおりでございます。
しかしながら、概算要求の後、財務省などとも意見交換を行った上で、政府が国家公務員の定員につきまして厳しい姿勢で合理化に取り組んでいること、他の行政機関も定員の再配置によって業務の増大に対処し、増員を抑制していることなどを踏まえまして、裁判所におきましても、国家機関として現有人員の有効活用を更に図れるかということを精査しまして、改めて増員の必要性について検討したところ、本年度は裁判所事務官九人の増員を図るということで、事件処理の支援のための体制強化を図ることができるというふうに考えたというものでございます。
○福島みずほ君
現在、国家公務員に関しては、やはり以前は新自由主義、減らせ減らせ減らせだったのが、ここ数年やっぱり雰囲気が変わってきたと歴然と思います。やっぱり人を減らせば公共サービスが実現できない、それからもう人が辞めていったり、できない。だから、やっぱりある程度、公共サービスのために国家公務員増やさなくちゃいけないという流れになっています。そして、どこの役所も必死です。新しい新規事業をやるから人を増やしてくれとか、組合も役所も必死で人員獲得をやっています。
裁判所も概算要求で四十三名増員要求しているわけじゃないですか。裁判所としてもやっぱりそれだけ増やしてもらわないと回らないと思っているからであって、九名というのは極めて残念だと思います。
裁判所、先ほどもありましたが、やはりこれ、人員要求、これから頑張ってやっていただきたい。いかがですか。
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君)
裁判所といたしましては、審理を迅速かつ適正に行っていくことは非常に重要であるというふうに考えております。そのために、審理運営の改善、様々な取組を進めておりまして、それを踏まえた人的体制を整備していくということが肝要であるというふうに考えております。
今後とも、引き続き必要な人員の確保に努めてまいりたいと考えております。
○福島みずほ君
是非、人員獲得、四十三名概算要求で出しているわけで、裁判所も分かっているわけですよ。人が増員しなくちゃいけない、それが九名で終わるということで、これから増員要求、私たちは応援団です、是非、様々増員するようにお願いします。
で、衆議院と参議院の附帯決議で、民法改正案の議論をしたときの附帯決議、衆議院では附帯決議七項、参議院では附帯決議九項、家庭裁判所の業務負担の増大及びDV、虐待のある事案への対応を含む多様な問題に対する判断が求められることに伴い、家事事件を担当する裁判官、家事調停委員、家庭裁判所調査官等の裁判所職員の増員が附帯決議で要求されております。
しかし、今回、家裁の調査官、僅か五名なんですよ、全国で五名。これ、ひどくないですか。

○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君)
お答えいたします。
今回、御指摘のとおり、家庭裁判所調査官につきましては、五名の増員をお願いしているというところでございます。これにつきましては、この調査官五人を増員することによりまして、改正家族法が成立したことを踏まえてより一層の家庭事件処理の充実強化を行うと、改正家族法の円滑な施行に向けた検討準備を含めて、その引き続き、引き続きその役割を果たしていくことができるのではないかというふうに考えております。
これは、家庭裁判所の事件動向を見ますと、少年事件におきましては近年大幅な減少傾向が継続しているというところがございます。家裁調査官は、少年に関する適正な処遇に資するよう、少年に対する調査のほか、学校等への関係機関への、関係機関や保護者を始めとする関係者に対する調査等を行い、それらの結果や処遇に対する意見を書面で裁判官に報告するなどの関わりをしているところでございます。
申し上げたように、少年事件は近年大幅な減少が続いているというようなこともございますので、裁判所の中で適切に応援体制、あるいは事務の分配を見直すといったことをしながら、各事件の適正な処理を進めていくことができる、そして、今回の五人の増員を踏まえて更に円滑な役割を果たし、役割を果たすべく円滑に進めていくことができるというふうに考えているところでございます。
○福島みずほ君
配付資料をお配りいたしました。
減少又は横ばいとされてきた事件数は一昨年から増加に転じています。少年事件しかり、家事事件しかり、刑事事件しかり。そして、少年事件に関しては、やはり特殊詐欺やいろんなものがあるので、闇バイトや、やっぱり事件が複雑かつ大変になっていると。大変です。
そして、ここの委員会で民法改正についての共同親権どうするとか議論がありました。これからたくさん、例えば親権、共同親権にする申立てや、いろんなものが出てくる。家庭裁判所の調査官は、いろいろ調べたり、周りの人の話を聞いたり、子供にも会ったり、物すごく労力を使います。
全国で五人きりって、ひどくないですか。改めて、別に減じていないじゃないですか。
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君)
お答えいたします。
申し上げましたとおり、今回、今年度に関しましては、家裁調査官について五名の増員をお願いしているところでありまして、この増員を含め、先ほど申し上げたような各事件の事件動向を見ながらの応援体制、あるいは事務分配、事務の見直しといったようなことをすることで、より一層の家庭事件処理の充実強化を行うということができるというふうに考えております。
また、改正家族法の施行、これもその検討の準備が進めることができるというふうに考えておりまして、今回このような増員をお願いしたというものでございます。
○福島みずほ君
今の答弁駄目ですよ。だって、附帯決議七項、衆議院、参議院のここの附帯決議九項でその増員をすることとなっていて、そして、これ五人って余りに少ないですよ。裁判官は増減なしですし、調査官は全国で僅か五名というわけですよね。これは本当にあり得ないと思います。
地域の裁判所充実へ全国組織が発足という記事を見ました。地域の裁判所の体制を充実させようと、全国四地域の行政や司法関係者らでつくる協議会が連携し、国に要望活動を行う全国組織が発足。長野県、神奈川県、新潟県などです。裁判官や家裁調査官が常駐していないなどの課題を抱えている。長野家裁佐久支部では、家事事件の件数は二千件を超えるが、長野家裁六支部のうち唯一調査官が常駐せず、上田支部の調査官が出張して対応している。また、大町出張所は裁判官がおらず、期日調整が制約される。全国各地で広がっています。
不足していますじゃないですか。調査官いないんですよ、常駐していない。裁判官がいないところがある。いかがですか。
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君)
お答えいたします。
裁判官あるいは調査官、家裁調査官といった者が常駐していない庁があるというのは御指摘のとおりでございます。これらの庁につきましては、事件数が少ないといった事情から、近隣の庁に配置されている裁判官あるいは調査官が当該庁の実情に応じて出向いていって事件を担当するというような体制を取っているところでございます。
全ての支部に裁判官を常駐させることが望ましいのかどうかというところにつきましては、そのような御意見もいただいているところではございます。裁判所も国の予算で運営される公的な機関でございます。業務量に見合った人の配置の在り方というのを考えていく必要があるというふうに考えております。
いずれにいたしましても、裁判所といたしましては、今後とも、事件数の動向等を常に注視しながら適正迅速な事件処理に支障の来すことのないよう対応し、今後とも全国津々浦々において利用者が適切な司法サービスの提供を受けることができるような必要な体制の整備に努めてまいりたいというふうに考えております。
○福島みずほ君
いや、考え改めてくださいよ。
長野家裁佐久支部では、家事事件の件数が二千件を超えるが、長野家裁六支部のうち唯一調査官が常駐しないということなんですよ。裁判官がいなかったり、調査官いなかったら本当に困るじゃないですか。
「虎に翼」で寅子ちゃんが行った三条の支部ですよね、裁判官が一人しかいないとかですね。でも、いなかったら令状発付とかどうなるんですか。本当にこれ大変ですよ。調査官いなかったら、きめ細やかなことができない。事件数がと言うけど、事件数多いところでいないんですよ。調査官、これから必要ですよ。地方こそ必要かもしれない。東京や大きいところはまあまあ人がいるかもしれないけれども、地方の疲弊は本当に際立っています。これ増やしていただけるようにお願いします。
そして、資料でもお配りしましたが、裁判官、今回も増減ゼロですが、があっと一般職が減っているんですね。前年度からの増減、一般職はマイナス四十七、二〇一五年からの累計ではマイナス二百八十八。調査官も裁判官もいないなんて冗談じゃないですよ。それ裁判所じゃないですよ。
で、不思議ですよね、最高裁。普通の役所は、増員してくれ、増員してくれなのに、裁判所は、間に合っています、間に合っていますで、とても不思議な役所で、とても不思議な役所ですよ。
裁判官と調査官がいないなんて裁判所じゃないですよ。弁護士だって困りますよ。だから、どうかこれはしっかり裁判所が回っていくように、三権分立の一翼を担う裁判所に頑張ってもらいたいからこそ、増員について応援をしていきたいというふうに思います。
裁判官の数も増やすべきですし、弁護士の任官が非常に少ないということも極めて問題だと思います。是非、働く人たちを応援する最高裁でいてください。よろしくお願いします。うんとうなずかれたので、よいということでしょうか。
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君)
お答えいたします。
裁判所といたしましては、全国津々浦々で均質な司法サービスが受けられるよう、これからも努力してまいります。また、必要な人員をきちんと確保をして、それぞれの庁において適切迅速な裁判が行われるよう、人的な体制も含めて今後とも検討してまいりたいというふうに考えております。
○福島みずほ君
頑張ってください。
増員を本当に必要だと、裁判官も職員も調査官も本当に必要ですので、さっき、うんとうなずいてくださったので、よろしくお願いいたします。
次に、国際人権に関する研修についてお聞きをいたします。
女性差別撤廃委員会の勧告、パラグラフ四十、裁判官に対し、雇用契約、雇用差別や雇用におけるジェンダーバイアスに異議を唱える際の条約及びその活用について研修を行う、勧告受けました。これをどう受け止められますか。
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君)
お答えを申し上げます。
裁判官の研さんということになりますと、OJT及び自己研さんが基本ではございますけれども、司法研修所におきましては裁判官に対して各種の研修を実施しております。国際的な人権に関する条約を含めたこれらの条約についての裁判官の意識を高めるために、国際人権法に関する研修も行っているところでございます。
○福島みずほ君
ただ、勧告はもっと具体的なわけで、雇用差別や雇用におけるジェンダーバイアスに異議を唱える際の条約及びその活用についてというふうにしています。
お手元に配付資料をお配りしています。裁判所における国際人権の研修について出してもらいました。まだまだまだまだ本当に少ない、足りないと思いますし、いかがでしょうか。
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君)
お答えを申し上げます。
裁判官の自己研さん、これを支援するために司法研修所においては様々な研修を実施しております。その中で、国際人権法に関する研修も実施しているというところでございます。また、できる限り多くの裁判官に研修内容に触れてもらえるように、国際人権法に関する研修を含めた一部の研修につきましては、研修に参加できなかったあるいは参加しなかった裁判官も含めまして、全国の裁判官が随時裁判所のポータルサイトを通じてその録画を視聴したり、用いられた資料を閲覧したりすることができるようにしているところでございます。
今後とも、裁判官において国際人権法に関する知見を高めることができるよう努めてまいりたいというふうに考えております。
○福島みずほ君
今までさんざんポータルで見れるとか閲覧しているとありましたが、効果が出ていないじゃないですか。だからこそ、女性差別撤廃委員会から勧告が出ているわけです。具体的にこれやってくださいよ。六十項目のあるうちの一項目なんですよ。裁判官に対するまさにこの雇用差別などについてやれというのは、はっきり具体的に書かれているんです。最高裁、これやるべきじゃないですか。
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君)
お答え申し上げます。
繰り返しになりますけれども、改めて、様々な研さん、研修等を通じまして、今後とも裁判官におきまして国際人権法に関する知見を高めることができるよう取り組んでまいりたいというふうに考えております。
○福島みずほ君
お手元に、国際人権条約に関する研修について最高裁が何をやっているかというのをお配りいたしました。
年一回、判事任官者研究会、新たに任官した判事ですが、障害者権利条約はやっていますけれども、あとはないんですよ。新任判事補研修も国際人権法で年一回です。ですから、まだまだ、いや、やらないよりはやった方がいいと思いますが、余りに少ない、余りに限られている。
もっと、拷問禁止条約、国際人権規約、子どもの権利に関する条約、女性差別撤廃条約など、障害者差別禁止条約、いろんなことで勧告も受けています。国際人権、日進月歩です。きっちり研修やるべきじゃないですか。
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君)
お答えを申し上げます。
今、司法研修所で行っている国際人権条約に関する研修でございますけれども、この中でも様々な条約に触れるような内容のものもございます。また、研修自体は、こう見ますと、数が少ないのではないかという御指摘もございました。先ほど申し上げたとおり、そういう点も含めまして、研修に具体的に参加できなかった者も含めて、この研修内容に触れてもらえるように、ポータルサイトを通じてその研修の録画を視聴したり、その資料を閲覧することができるようにしているところでございます。
引き続き、様々な工夫をしてまいりたいというふうに考えております。
○福島みずほ君
今まで、閲覧ができるようにしているとか回覧しているとかポータブルで見れるようにと言うけど、効果が、まあ見る人は見るかもしれませんが、きちっとした研修をやるように心から要請しますし、この法務委員会でこれからも聞いていきます。
それで、検察庁、それから人権擁護局、出入国管理庁、それから矯正局などでどのような研修をやっているかの資料もいただきました。正直、まだまだ足りないですね。検察官は、新任検事研修、検事一般研修及び検事専門研修について、いずれも四十五分、ただし直近二回の新任検事研修は二十五分の研修、これは新任だけですし、少ないですよね。
もっと、国際人権規約、政治的、精神的自由権に関する規約委員会からは、法務省の関係することがたくさん勧告をされています。入管も、刑務所も、取調べも、人権もたくさん、法務省の関係するものが圧倒的に多いじゃないですか。
この検察官の研修だってとても少ないというふうに思っています。いかがですか。

○政府参考人(堤良行君)
お答えいたします。
法務省及び出入国在留管理庁におきましては、人権についての理解を深めるため、例えば検察庁に関しましては、新たに任官した検事、任官後三年前後の検事、任官後七年ないし十年の経歴を有する検事に対し、人権諸条約等に関する研修を毎年実施しております。出入国在留管理庁に関しましては、全職員に対し、外国人の人権を含む人権に関する研修を令和三年度以降毎年実施しているほか、業務の中核を担う職員に対し、外国人の人権や人権諸条約に関する研修を毎年実施しております。矯正局に関しましては、採用時及び幹部任用時に該当する全ての矯正職員に対し、国際準則等を含む人権に関する研修を毎年実施しております。人権擁護局に関しましては、法務局、地方法務局の人権擁護課長等に対し、人権諸条約を含む人権に関する研修を毎年実施しております。
これらの研修に加えまして、日常の業務を遂行する中でも、上司から部下職員に対しまして人権擁護の観点から適切に指導を行うなど、職員の人権についての理解を深めるよう取り組んでおります。
こうした取組により、職員の人権に関する理解がより深まるよう努めてまいりたいと考えております。
○福島みずほ君
資料もいただきましたが、まだまだ不十分だと思います。
人権擁護局が作った、法務省が動画サイトに掲載している人権啓発動画も見ました。なかなか工夫しているとは思いますが、しかし、入管も刑務所もそれから取調べも人権侵害がたくさん起きている部門です。法制度上も問題があるし、実際運用上も人権侵害が起きている。ですから、この中身の国際人権の研修では不十分だし、法制度上の見直しが必要だと思います。
検事総長に関して、きちっとここに来てもらって、袴田事件についてきちっと検証するということが必要だと考えます。
袴田事件に関して集中審議を行っていただくよう強く申し上げます。委員長、お願いします。
○委員長(若松謙維君)
後刻理事会で協議いたします。
○福島みずほ君
是非、袴田事件という冤罪事件に関して、しっかり、なぜこういうことが起きたのか、集中審議をこの法務委員会はやるべきだと思います。そこに検事総長も来ていただいて、とことんやって、人権侵害をなくす。人権啓発も大事です。でも不十分です。そして、人権侵害が実際起きていることに関して、法務省、これはしっかりやるべきだと思います。
判検交流についてお聞きをいたします。
裁判官とそれから検事の交流はなくなりました。しかし、訟務検事の制度、つまり裁判官がまさに法務省に勤務し、国の代理人となって、あるいはその後、裁判所に戻る。つまり、国の代理人となって、そして今度は裁判官、中立的なふりをしてと言うと悪いけど、中立的なように出る、これはやめるべきだと思います。
訟務検事の数は減少していません。出向裁判官は二〇二四年で百六十八人、法務省に勤務している裁判官出向者の訟務局には二十三人です。これはもうやめるべきじゃないですか。やめるべきじゃないですか。
○国務大臣(鈴木馨祐君)
まず、私どもといたしましては、法曹間のこの人材交流というか、そういったことについては、まさにこの法務省の所掌事務の適正な処理であったり、あるいは国民の期待、信頼に応える多様で豊かな知識、経験を備えた法曹の育成、確保のためにもこれは必要だと考えているところであります。
その上で、今御指摘ありました訟務の関係でありますけれども、国を当事者とする訴訟でありますけれども、まさにその結果が政治、行政、経済等に重大な影響を及ぼし得る重大大型事件が増加傾向であるということもありますし、あるいは事件の内容、これも非常に複雑化、困難化をしているところがあります。
そういった中にあって、法律による行政の原理を確保して適正な訴訟追行を行うという観点から、訟務部局に、まさにそうした幅広い視点を持っている、そうした裁判官出身者の方についてもこの人材として配置をすること、これは重要な意義を有していると我々としては考えているところであります。
そういったことから、訟務分野における裁判所出身者、これを減らす、あるいはなくした方がいいという御指摘でありますけれども、私どもとしては、減らせば減らすほどよいということでは必ずしも考えていないところでございまして、やはり様々な観点から見たバランス、これを重視をして人材を配置をしていくことが必要ではないかと考えております。
○福島みずほ君
バランスがぶっ壊れているんですよ。だから、裁判官と検察官の交流はなくなりました。裁判所から裁判官借りてきて、国の代理人、一方当事者にするんですよ。公平な裁判なんてできないじゃないですか。その裁判官がまた裁判所に戻るんですよ。国の代理人やって、国を訴える裁判の裁判やるんですよ。公平じゃないじゃないですか。
検察官と裁判官の交流はなくなりました。今度はこの訟務検事なくしてくださいよ。なくすべきですよ、この二十三名。バランスでちょっと能力がある人を借りる話じゃないんですよ。その人、裁判官として戻って裁判やるんですよ、国の代理人やって。これは問題だと思います。訟務検事、この制度をなくす、なくすよう、大至急なくすよう強く要望し、私の質問を終わります。
※本議事録は未定稿です。